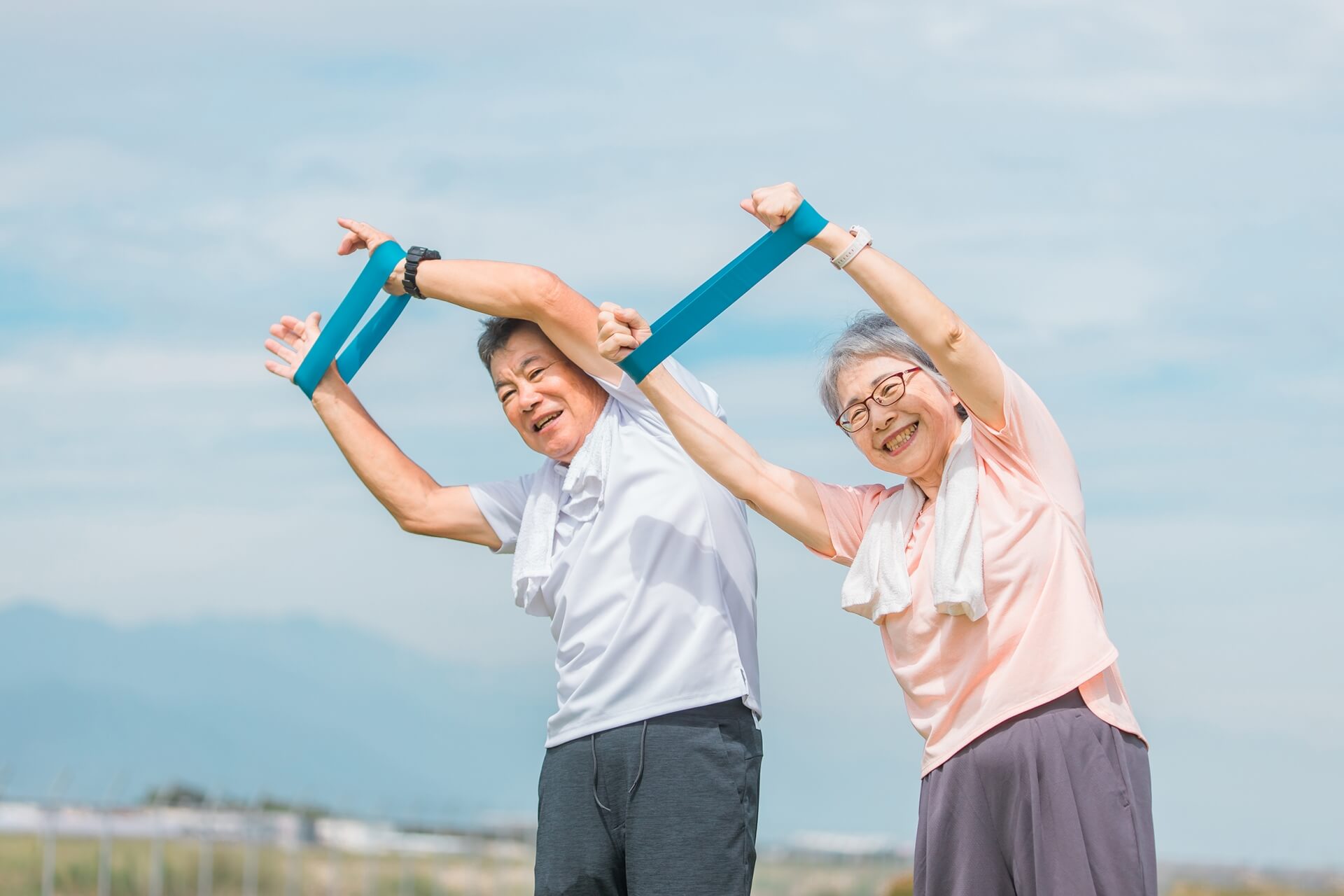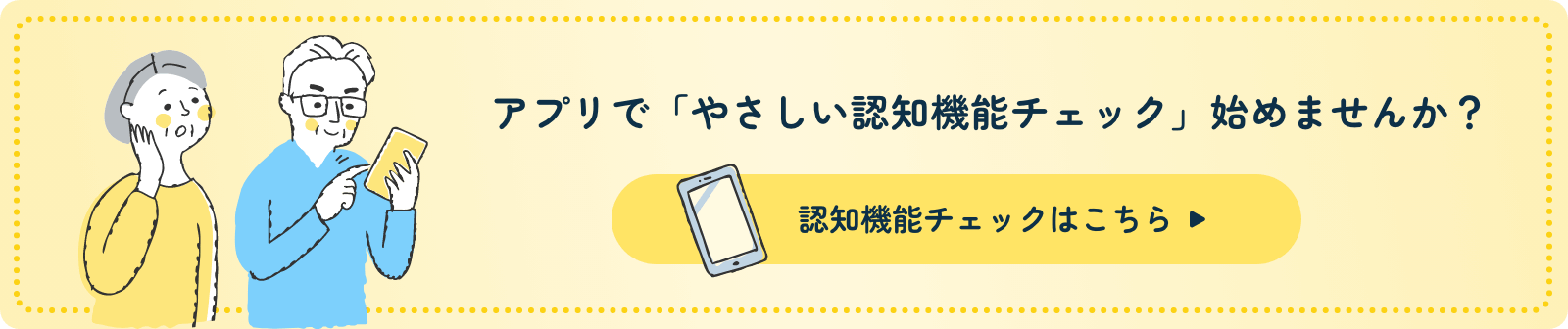認知症予防はいつから始めるべき?始めるタイミングと5つの予防法

「認知症は年を取ったらなるものだから高齢になってから予防すればいいでしょ」
「認知症予防はいつから始めたらいいの」
このように思っていたり、不安を感じていたりする方も多いのではないでしょうか。
厚生労働省によると、認知症の方は2025年に675万人〜730万人になると推測されており、実に65歳以上の5人に1人は認知症になると見込まれているのです。
この記事では、認知症の予防を始めるタイミングや予防方法を解説します。
いつから取り組めばよいか悩んでいる方の助けになると幸いです。
目次
認知症の予防はいつから始めるべき?

「認知症は年を取ってからなるもの」と思っていませんか?
しかし、研究により、45~49歳の中年期から認知機能の低下が始まると報告されており、脳の病理変化はすでに中年期から始まっているのです。
認知症と関係のある生活習慣病もまた、中年期が気をつけたい病気です。
特に、45~64歳の中年期に高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満(メタボリックシンドローム)・脳卒中にかかっている場合や、65歳以上の高齢期に糖尿病・脳卒中だと認知症の危険が高まると言われています。
40代で生活習慣病であれば、その時点で認知症になりやすいと言えるのです。
「認知機能の低下がわかってから」もしくは「生活習慣病を指摘されてから」予防を始めるのではなく、取り組もうと思ったいまから予防に努めることが重要です。
認知症予防の3つの段階

認知症予防は、以下の表のように「一次予防」「二次予防」「三次予防」の段階があります。
| 予防の段階 | ポイント |
|---|---|
| 一次予防 | 認知症の発症を遅らせたり、発症のリスクを軽減したりする |
| 二次予防 | 認知症を早く発見し、早期対応につなげる |
| 三次予防 | 認知症の重症化を予防する |
予防するためには、病気になる前から取り組む「一次予防」が大切です。
正常な状態と認知症の間には軽度認知障害(MCI)の状態があります。
このMCIの状態でどのような取り組みを行うかによって、認知機能は回復・維持・低下のいずれかに進みます。
「高齢期になってから」「生活に困ることが出てきてから」ではなく、今できることから始めましょう。
今からできる認知症予防のための5つの対策

ここでは、予防するために今から取り組める対策を紹介します。
それぞれの対策を知って、できることから始めてみましょう。
食生活に気をつける
予防のためには、食生活に気をつけることが重要です。
栄養バランスのとれた食事で糖尿病や高血圧などの生活習慣病を予防することは、認知症の予防にもつながります。
米国で開発されたDASH食(脂肪を多く含む肉類を減らし、果物、野菜、低脂肪乳製品などを積極的に摂る)は高血圧予防・治療のための食事療法です。
また、オリーブオイル、果物、野菜、ナッツ、豆、魚、穀物を中心に使用する地中海式食事法は、認知症予防になる可能性が報告されています。
ただし、DASH食と地中海式食事療法を組み合わせたMIND食は、認知症予防効果が確認できていません。
特定の食事療法にこだわりすぎず、まんべんなく栄養素を摂るように心がけることが大切です。
特に、主食を控えて以下の「食品が摂れるおかず」を充実させる食事パターンが推奨されています。
- 大豆・大豆製品
- 緑黄色野菜
- 淡色野菜
- 海藻類
- 牛乳・乳製品
- 果物・果物ジュース
さらに、さまざまなスパイスが入っているカレーも予防におすすめです。
詳しくは下記の記事を参考にしてください。
運動する
活動的な生活習慣は脳の健康に関わっており、認知症予防には欠かせません。
運動しない場合と比べて運動をする場合は認知症を発症しにくかったと報告されています。
運動の例としては、有酸素運動の1つであるウォーキングなどがおすすめです。
下記の記事で具体的な運動やウォーキング方法を解説していますので参考にしてみてください。
禁煙する
タバコを吸うと、糖尿病や高血圧などの生活習慣病になりやすく、その結果、認知症のリスクが高まります。
タバコを吸う期間が長くなるとリスクも高まるため、喫煙している人は、できる限り早い禁煙が必要です。
ただし、タバコに含まれるニコチンの影響で自力で禁煙できない方もいるでしょう。
その際は、ニコチンパッチやニコチンガムといった禁煙のサポート薬を使ったり、禁煙外来で相談したりしてみてくださいね。
過剰なアルコール摂取を控える
アルコール依存症や大量の飲酒者には脳の萎縮がみられ、認知症になりやすくなるため、アルコールの過剰摂取を控えることが重要です。
認知症のリスクが低くなるのは、350mlのビールを1~6本/週程度の飲酒と言われています。
そのため、お酒を飲む量や飲み方を考えて、たしなむ程度に楽しむことが大切です。
聴力低下の対策をする
聴力の低下は加齢とともに起こり、認知機能の低下や認知症の発症と関連しています。
難聴があると、もの忘れの自覚、不安感、焦燥を感じる割合が多く、ほかの人とコミュニケーションをとりにくくなったり、孤独感・孤立感を感じやすくなり、認知症になりやすいと言います。
補聴器を適切に用いることで、認知症のリスクが軽減したという報告もあります。
聞こえの低下を感じたら、まずは耳鼻科に相談しましょう。
補聴器が有効であるか検査・診断を受けることが必要です。
認知症予防はなるべく早くから
認知機能の低下は、45〜49歳の中年期からすでに始まるとされているため、中高年になる前の今から認知症予防に取り組むことが大切です。
運動したり食生活に気をつけたりすることで、認知症の一因である生活習慣を予防できます。
まずは、自分の認知機能がどのような状態か知っておかなければなりません。
そこで、「ベルコメンバーズアプリ」の認知機能チェックを活用してみてはいかがでしょうか。
認知機能をたった数分のチェックで確認できます。
無料で利用できるので、早速登録してみてくださいね。

監修者
浦上 克哉 教授

監修者
浦上 克哉 教授
日本老年精神医学会理事
日本老年学会理事
日本認知症予防学会専門医
1983年鳥取大学医学部医学科卒業
1988年同大大学院博士課程修了
1990年同大脳神経内科・助手
1996年同大脳神経内科・講師
2001年同大保険学科生体制御学講座環境保健学分野の教授(2022年まで)
2016年北翔大学客員教授(併任)
2022年鳥取大学医学部保健学科認知症予防学講座(寄付講座)教授に就任
読まれている記事一覧
-

高齢者が同じことを何度も言うのはなぜ?対応方法と認知症との関連性を解説
-

認知症で病院に入院できる!精神科に入院する3つの基準や期間を解説
-

80代の親が少し前のことを忘れるのは単なる物忘れ?認知症との違いや見分ける方法を解説
-

高齢の母親と話が通じない4つの理由|コミュニケーション改善法やストレス対策も解説
-
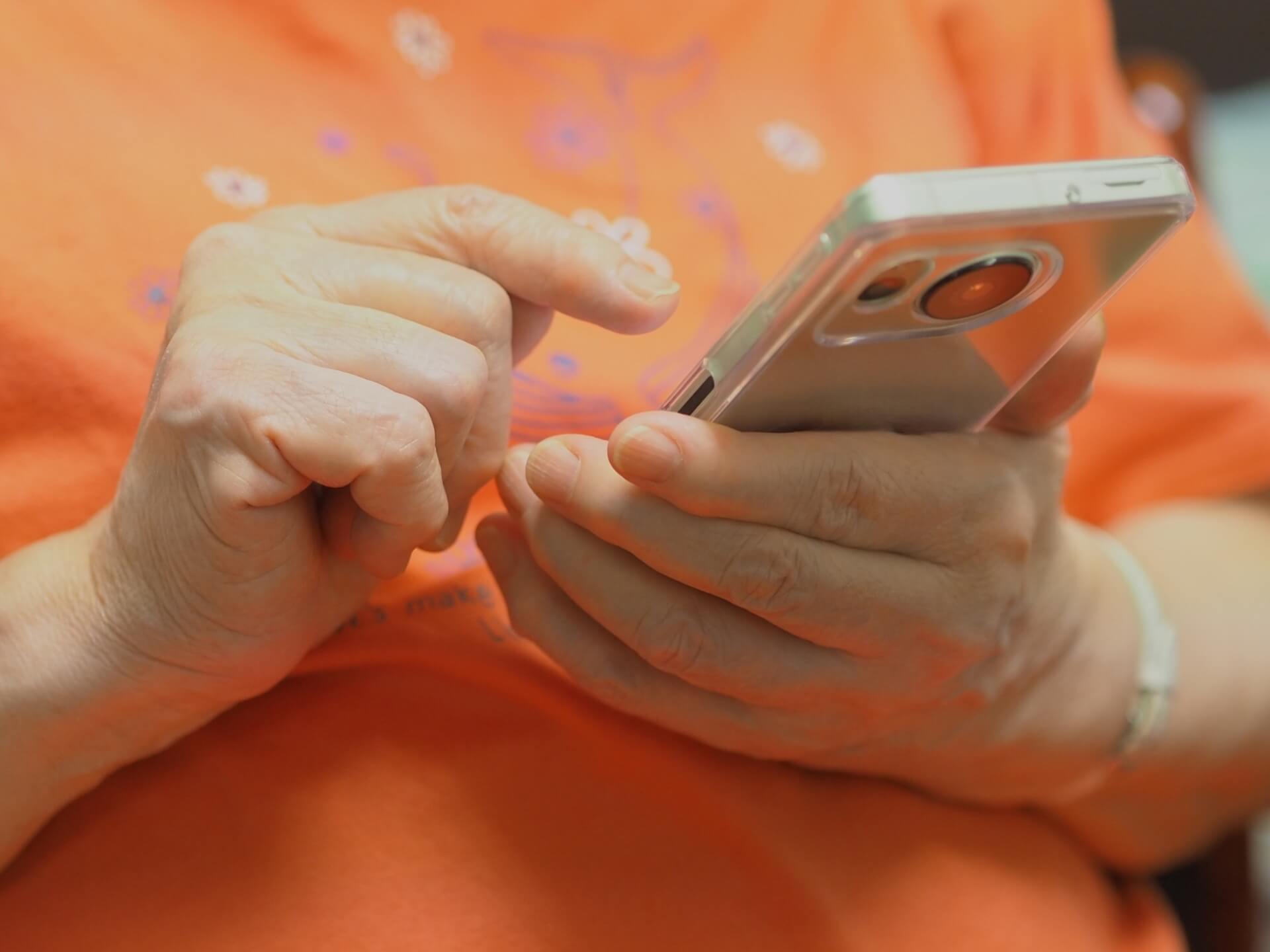
認知症予防に役立つチェックアプリ3選!おすすめポイントも紹介
-

認知症の親を施設に入れるタイミングと注意点を徹底解説
-

高齢の親が寝てばかりいるのは認知症の初期症状が原因?家族ができる対処法3選
-

認知症の原因物質であるアミロイドβとは?溜まる3つの原因や排出方法紹介
-

同じ話を繰り返す母親への対処法|2つの原因と認知症チェック方法も徹底解説
-

認知症の予防にはコミュニケーションが効果的!4つの方法も紹介
-

認知症の初期症状はわがまま?早く対処すべき3つの理由とその対処法
-

英語を話せると認知症になりにくい?予防のための学習法をお伝えします
-

【無料プリントあり】認知症予防に役立つプリントの活用方法と選び方
-

麻雀が認知症予防に?楽しみながら脳を使って健康に
-

認知症の症状を抑える方法は主に3つ!治った例や家族の対応ポイント