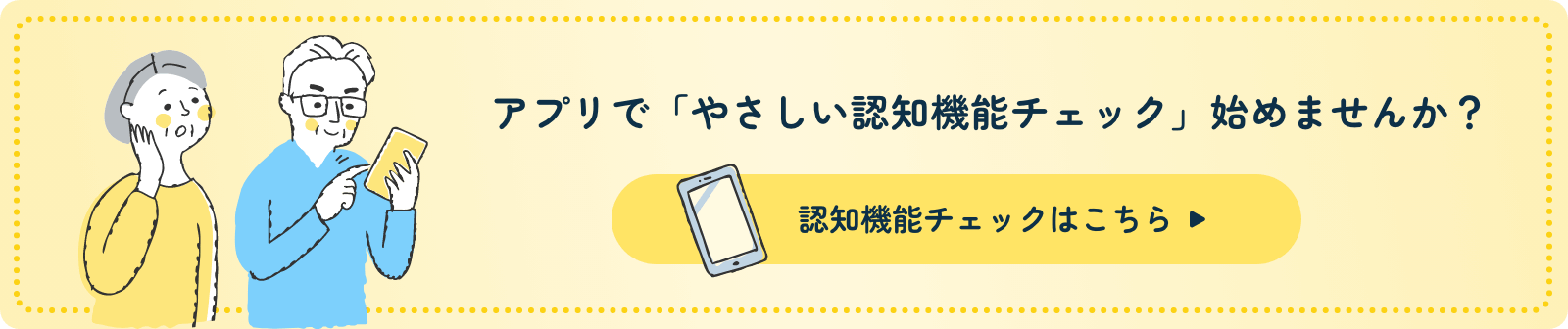認知症の症状を抑える方法は主に3つ!治った例や家族の対応ポイント

「認知症を治す方法はあるの?」「認知症になったらどんな治療をするの?」
このように悩んでいる方はいませんか。
認知症は根本的な治療が難しい場合がある一方で、認知症の原因を取り除くことで治療できる場合があります。
さらに、治療が難しいときは「進行を緩やかにする」治療やケアが大切になるでしょう。
この記事では認知症を治す方法や家族や周囲の人ができることなどについて解説します。
認知症を治す方法があるのか不安を感じているあなたが、この記事を読んで悩みを解決できると幸いです。
目次
認知症の症状を抑える方法は主に3つ

はじめに、認知症の治療は大きく「3つ」にわけられ、それぞれ認知症の方の状態や症状に合わせておこないます。
- 1.薬物療法
- 2.非薬物療法
- 3.外科的手術
では、それぞれの治療内容についてお伝えします。
1.薬物療法
認知症に使われる薬は「認知機能障害」に対するものと「行動・心理症状」に対するものがあります。
それぞれの薬の種類は、以下のとおりです。
- 認知機能障害:コリンエステラーゼ阻害薬・NMDA受容体拮抗薬 など
- 行動・心理症状:抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬、漢方薬 など
認知症の治療で使う薬は「認知症を治す」ものではなく「症状の進行を遅らせる」ことが目的です。
また、薬物療法では副作用があらわれる恐れがあるため、少量から開始し、認知症の方の様子を見ながら薬の量や種類を調整します。
とくに、高齢者は副作用が現れやすいため、後述する非薬物療法から開始し、効果が乏しい場合に薬物療法を検討することもあります。
薬を飲み始めて様子の変化や気になることがある場合は、早めに主治医に相談しましょう。
2.非薬物療法
非薬物療法には以下のようなさまざまな種類があります。
| 非薬物療法 | ポイント |
|---|---|
| 認知機能訓練 | 記憶や注意、問題解決力など個々のレベルに合わせた課題をおこなう |
| 音楽療法 | 音楽を聴く、歌う、演奏する、リズム運動などをおこなう |
| 認知リハビリテーション | 日常生活の改善に焦点をあて、失った機能を補う方法の獲得を目標とする |
| 認知機能訓練 | 記憶や注意、問題解決力など個々のレベルに合わせた課題をおこなう |
これらの治療法は、認知機能の低下だけでなく、不安や興奮などの行動・心理症状と日常生活機能の改善を目標としています。
また、認知症を改善することにくわえて、本人の生活の質(QOL)や生きがいの維持するために、医療者や介護者とのつながりを築くことも大切なポイントです。
3.外科的治療
認知症を生じている原因によっては、手術で認知症の回復が見込まれる場合があります。
たとえば、水頭症や慢性硬膜下血腫、脳腫瘍などが原因で認知症を引き起こしているケースです。
これらの病気は、正常な脳が圧迫されていることで認知症が現れている場合があり、手術によって原因を取り除くことで症状が改善することがあります。
例に挙げた病気は、高齢者に多いものでもあるため「認知症かな?」と気になる症状があるときは、早めに病院を受診しましょう。
認知症で治った2つの事例

ここでは、治療により認知症が治った事例をご紹介します。
事例1:髄膜腫の手術を受けて認知症が治った例
「骨髄腫」という脳を覆っている膜から生じる腫瘍は、脳を外から圧迫しながらゆっくりと大きくなるため、無症状のまま経過することが多い病気です。
大きさが3㎝を超えると脳への圧迫が強くなり、認知症の症状が出やすくなります。
腫瘍を摘出する手術をおこなうことで、認知症の改善がみられたひとつの例です。
事例2:甲状腺の治療を受けることで認知症が治った例
甲状腺の機能が低下し、ホルモンの分泌が低下すると疲れやすさや無気力などが現れます。
活動性が低下するために認知症と診断されることがありますが、甲状腺の治療で症状は改善したという報告があります。
認知症の方の家族や周囲の人ができること

認知症の対応は、介護者の負担も大きいものです。
そのため、介護者のケアも重視し、負担が大きくならないよう精神面へのケアやサービス調整の検討が必要とされています。
認知症の症状への適切な対応を知る
認知症の方が「何度も同じことを聞いて困る」ということもあるでしょう。
はじめは丁寧に対応していても、繰り返し聞かれると介護者も疲れてしまいます。
しかし、本人も悪気があるわけでなく、もしかしたら何か不安があるのかもしれません。
本人の想いを聞いてみると、答えがわかることがあります。
適切な対応やケアを知るために、主治医に適切な方法を確認したり、医療スタッフにケアについて指導を受けたりしましょう。
認知症の方が利用できる介護サービスを検討する
認知症の方を家族だけで介護することは負担が大きく、長期間続けることは難しいでしょう。
そこで、介護サービスの利用を検討してみるのも一手です。
なかには、介護サービスの利用を敬遠される方もいるかもしれません。
ただし、家族の方にとって息抜きとなり、専門的な知識をもったスタッフへ相談したり、認知症の方が家族以外と関わりを持てたりする機会でもあります。
どのような介護サービスが利用できるのか、ケアマネジャーやお住まいの市区町村の介護窓口に相談してみてください。
認知症の方との生活について考える
「人生会議(アドバンス・ケア・プランニング<ACP>)」の考え方が広まっています。
これは「もしものときにどうするか」を前もって考え、家族や周囲の人と共有しておく考え方です。
今後の生活や病気の治療方法などについて考えておくことは、何かあったときでも本人の意思に沿った生活を実現することにつながります。
とはいえ、認知機能が低下している場合、本人の意思の確認が難しいこともあるかもしれません。
そのときは、本人のこれまでの歴史や価値観などを考えて、家族や医療スタッフと情報を共有し、本人が望むことを考えてみてください。
認知症の方との関わりがある人からのさまざまな視点からの情報が、よりよい選択になるでしょう。
まとめ
認知症は完治が難しいとされており、治療のおもな目標は「症状の進行を遅らせる」ことです。
そのため、認知症を早く発見し、治療を開始することが重要です。
そのため、自分の認知機能をチェックしてみませんか?
「ベルコメンバーズアプリ」では、お手軽にチェックできます。
まずは登録してみてくださいね。
読まれている記事一覧
-

高齢者が同じことを何度も言うのはなぜ?対応方法と認知症との関連性を解説
-

認知症で病院に入院できる!精神科に入院する3つの基準や期間を解説
-

80代の親が少し前のことを忘れるのは単なる物忘れ?認知症との違いや見分ける方法を解説
-

高齢の母親と話が通じない4つの理由|コミュニケーション改善法やストレス対策も解説
-
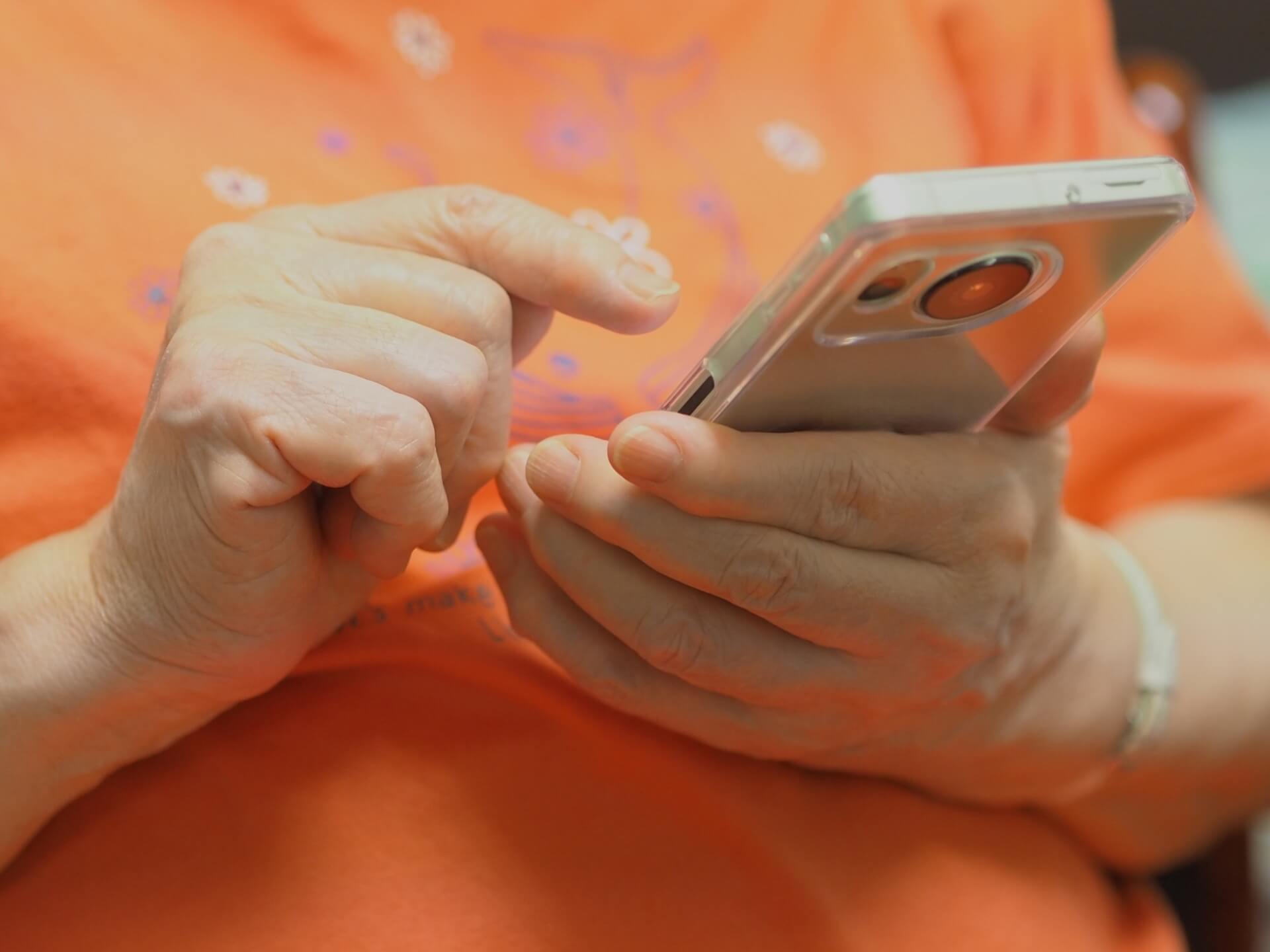
認知症予防に役立つチェックアプリ3選!おすすめポイントも紹介
-

認知症の親を施設に入れるタイミングと注意点を徹底解説
-

高齢の親が寝てばかりいるのは認知症の初期症状が原因?家族ができる対処法3選
-

認知症の原因物質であるアミロイドβとは?溜まる3つの原因や排出方法紹介
-

同じ話を繰り返す母親への対処法|2つの原因と認知症チェック方法も徹底解説
-

認知症の予防にはコミュニケーションが効果的!4つの方法も紹介
-

認知症の初期症状はわがまま?早く対処すべき3つの理由とその対処法
-

英語を話せると認知症になりにくい?予防のための学習法をお伝えします
-

【無料プリントあり】認知症予防に役立つプリントの活用方法と選び方
-

麻雀が認知症予防に?楽しみながら脳を使って健康に
-

認知症の症状を抑える方法は主に3つ!治った例や家族の対応ポイント