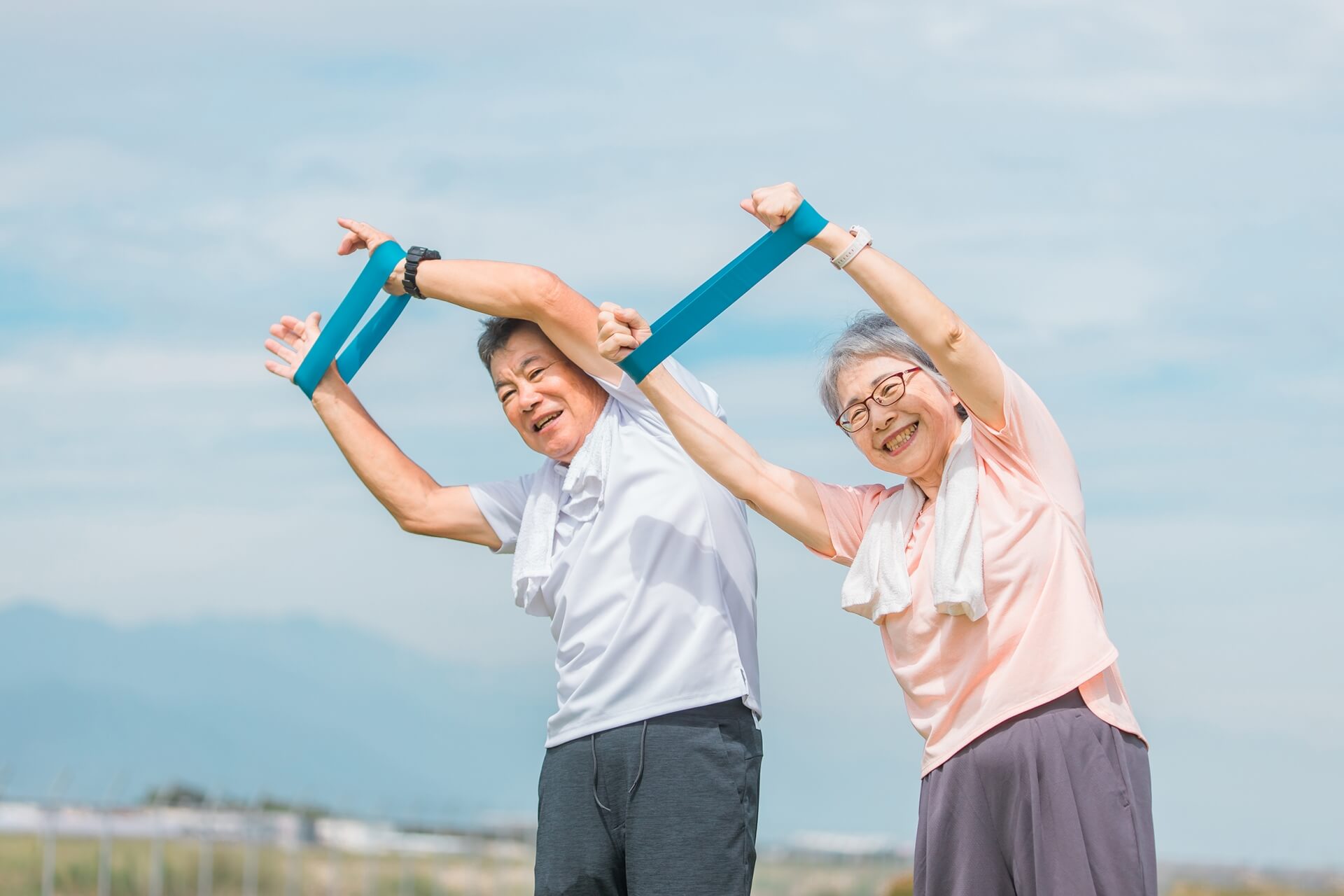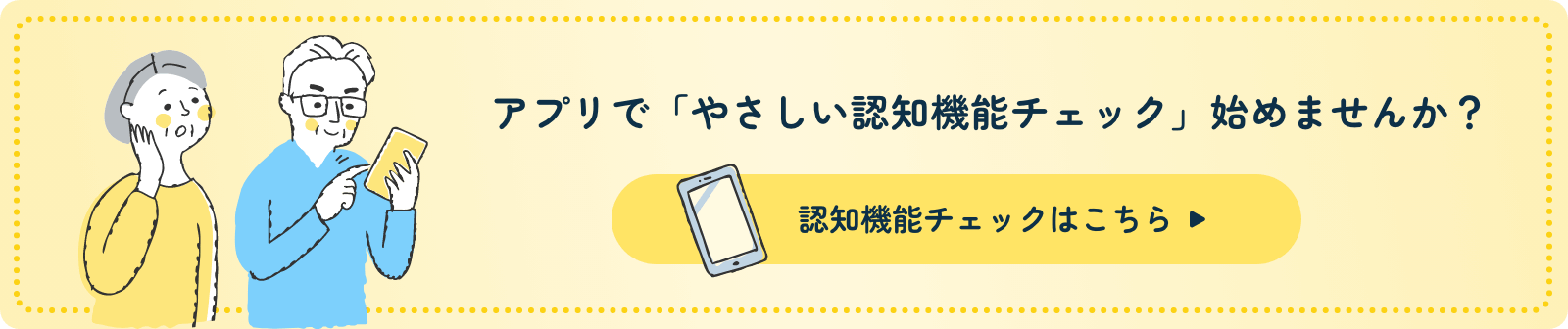麻雀が認知症予防に?楽しみながら脳を使って健康に

「認知症になりたくないから予防法を知りたい」「麻雀が認知症の予防になるって本当?」
このような疑問や心配を感じたことはありませんか?
麻雀に不健康なイメージを持たれている方もいるかもしれませんが、実は認知症予防が期待できる活動として注目されています。
健康づくりとしての健康麻雀や、麻雀特有の特徴が与えるよい影響について詳しく解説します。
「認知症になるかもしれない」と不安を感じている方々が、その不安を少しでも軽減できるきっかけになれば幸いです。
目次
認知症予防に「健康麻雀」

健康麻雀は日本健康麻将協会が健全な頭脳スポーツとして普及・推進している麻雀です。(協会では「健康麻将(マージャン)」の表記です。)
麻雀は「タバコを吸い、お酒を飲んでお金を賭ける」という不健康なイメージを持つ方も多いでしょう。
健康麻雀は「吸わない・飲まない・賭けない」というルールのもとで行われます。
ゲームとしての楽しみだけではなく「健康づくり・仲間づくり・生きがいづくり」に有効とされることから、内閣府のエイジレス・ライフ実践事例としても取り上げられています。
脳によい影響を与える活動として、複数の自治体によって、健康麻雀教室や大会なども積極的に開催されています。
麻雀が認知症予防によいと言われる4つの特徴

軽度〜中等度の認知機能に障害がある高齢者が週に2回(1回1時間)、合計12週間麻雀を行うことで、短期記憶などに改善が認められたという報告もあります。
ここでは、麻雀がもたらすよい影響について解説します。
麻雀は指先をよく使う
麻雀は、終始小さな牌(パイというコマのこと)を並べたり、入れ替えたりする独特の指先操作が求められます。
たとえば、手元にあるバラバラに並んだ牌をわかりやすく並び替える「理牌(リーパイ)」、山から牌を取る「取牌(チュパイ)」、 場に捨てる「打牌(タァパイ)」の動作は、指先で牌をつまんで立てる、裏返すなど、指先の細かい操作が繰り返し必要です。
ゲーム開始前に牌をシャッフルする「洗牌(シーパイ)」や、自分の前に牌を2段に積み重ねて山を作る「砌牌(チイパイ)」は両手を使います。
このように指を動かす機会が多いと、脳が活性化すると言われています。
麻雀は頭をよく使う
麻雀牌は34種類あり、それぞれ4枚ずつ用意されています。
この合計136枚の牌の組み合わせで決まる多くの「役」があり、「役」を作り出してアガリをめざします。
麻雀は次のようによく頭を使うゲームです。
- アガリの形、「役」などのルールを覚える
- 手持ちの牌を見て「役」を作るための手段・戦略を考える
- 相手がどのような手でアガリをめざしているかを予想する
- 状況に応じて戦略を変更し、柔軟に対応する
- 「役」ごとの点数を覚え、計算する
「役」などのルールを覚え、対戦中は繰り返し考え、あがったら計算してというように、常に脳を使い続けます。
このように、頭を使うゲームや課題は、種類によって脳の使われる部分も異なりますので麻雀に限らず、英会話やプリント課題など、さまざまな活動に取り組むのがよいでしょう。
認知症の予防には、頭を使う課題と身体を使う課題の両方を行うことがより効果的と言われています。
ウォーキングや筋トレなども組み合わせて、自分に合った予防法に取り組んでみてください。
麻雀はコミュニケーションが自然に生まれる
麻雀は基本的には4人で麻雀卓を囲んで行うテーブルゲームです。
相手が捨てた牌が欲しい時には声を発して「捨牌(ステハイ)」をもらうルールもあり、自然とコミュニケーションが生まれます。
友人や仲間とのコミュニケーションは認知症予防につながります。
他者との交流が週に1回もない場合、認知症を発症しやすくなると言われているので、麻雀などの共通の趣味を通して、仲間と週に1回以上は交流することが大切です。
麻雀が社会参加のきっかけになる
認知症を発症する要因の1つに社会的な孤立があります。
家族や友人、近所の人など、誰とも交流する機会がないと、認知症のリスクが高まります。
これまで、麻雀は雀荘ですることが一般的でした。
しかし、近年では高齢者の間で麻雀の人気が高まっており、以下のような場所でも実施されています。
- 公民館
- カルチャーセンター
- 介護施設
麻雀を打ちに施設に通うことが外出するきっかけとなり、運動やリフレッシュにもなるでしょう。
麻雀を仲間と楽しむだけではなく、麻雀初心者への指導を通して活躍するなど、社会的な役割を持つきっかけになるかもしれません。
麻雀を通じた社会参加が認知症の予防につながるでしょう。
認知症予防をめざせるゲームは麻雀以外にも

麻雀以外にも、「トランプ、囲碁、将棋」は認知症予防が期待できるという報告があります。
トランプ
トランプを時々、または定期的に行っている高齢者は全く行っていない人よりも認知機能検査において結果が優れていたことが報告されています。
囲碁
認知機能の低下がみられる高齢者を対象に定期的に囲碁をプレイした調査では、注意機能とワーキングメモリが改善・維持されたとあります。
将棋
将棋が脳の尾状核(学習や記憶などの認知機能に関わる部分)の活性化を促すと報告されています。
限られた対象での報告ではあり、今後の詳しい研究結果が望まれますが、ボードゲームは麻雀と同じように指先を動かし、他者とコミュニケーションを取る活動です。
認知症の予防に前向きな効果が期待できると言えるでしょう。
楽しく脳を使って認知症を予防しよう
麻雀はゲームを楽しみながら指先を使ったり、仲間と話したりするため、認知症予防が期待できる活動として注目を集めています。
認知症は認知機能が段々と低下して、やがては日常生活に支障をきたすようになる病気です
症状が進んでいない段階で見つけられると認知機能が改善することもあるため、早期発見が重要です。
そこで、早期発見に役立つ「ベルコメンバーズアプリ」を活用してみてはいかがでしょうか。
認知機能がどのくらい変化しているのかをゲーム感覚で知ることができます。
無料で利用できるため、まずは登録してみてくださいね。
読まれている記事一覧
-

高齢者が同じことを何度も言うのはなぜ?対応方法と認知症との関連性を解説
-

認知症で病院に入院できる!精神科に入院する3つの基準や期間を解説
-

80代の親が少し前のことを忘れるのは単なる物忘れ?認知症との違いや見分ける方法を解説
-

高齢の母親と話が通じない4つの理由|コミュニケーション改善法やストレス対策も解説
-
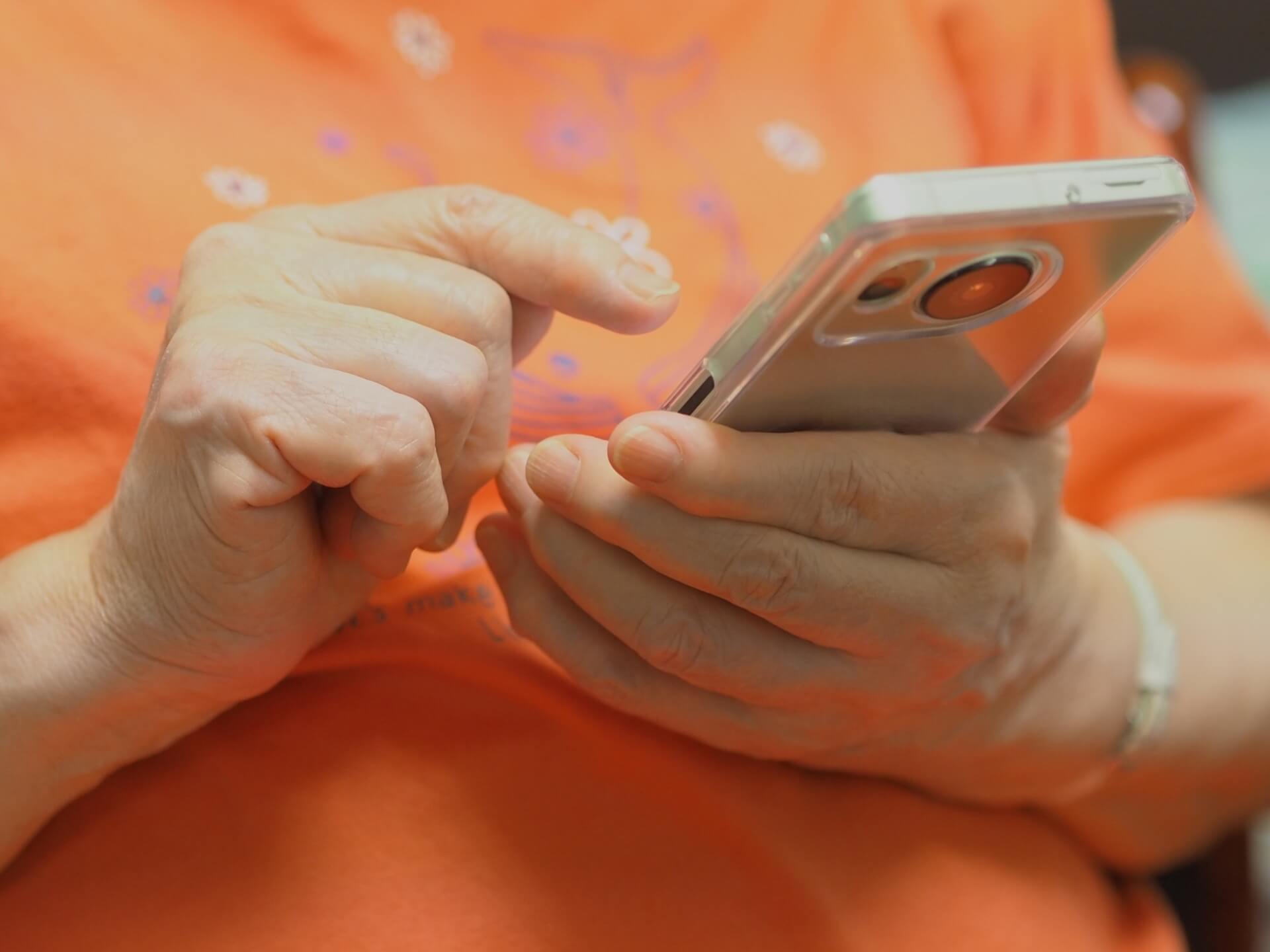
認知症予防に役立つチェックアプリ3選!おすすめポイントも紹介
-

認知症の親を施設に入れるタイミングと注意点を徹底解説
-

高齢の親が寝てばかりいるのは認知症の初期症状が原因?家族ができる対処法3選
-

認知症の原因物質であるアミロイドβとは?溜まる3つの原因や排出方法紹介
-

同じ話を繰り返す母親への対処法|2つの原因と認知症チェック方法も徹底解説
-

認知症の予防にはコミュニケーションが効果的!4つの方法も紹介
-

認知症の初期症状はわがまま?早く対処すべき3つの理由とその対処法
-

英語を話せると認知症になりにくい?予防のための学習法をお伝えします
-

【無料プリントあり】認知症予防に役立つプリントの活用方法と選び方
-

麻雀が認知症予防に?楽しみながら脳を使って健康に
-

認知症の症状を抑える方法は主に3つ!治った例や家族の対応ポイント