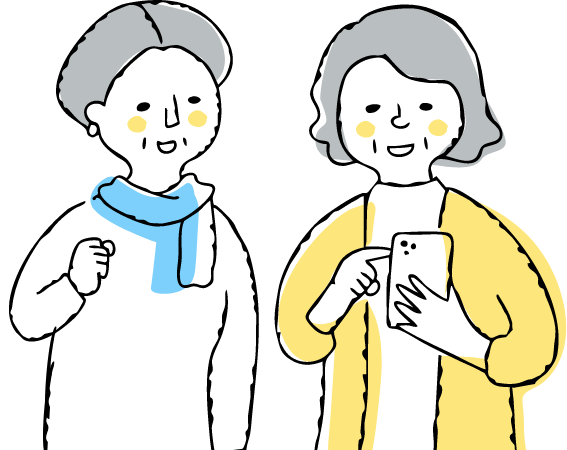認知症の基礎知識
認知症の基礎知識
― 大切な人の「気になる変化」に、
やさしく寄り添うために ―

 認知症の基礎知識
認知症の基礎知識― 大切な人の「気になる変化」に、
やさしく寄り添うために ―
「最近、もの忘れが増えてきた気がする。認知症の初期症状なのかな。」
「家族が同じことを何度も聞くようになってきたような…。」
「認知症のこと、誰に相談すればいいのか分からない。」
そんなふとした不安から、このページをご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれません。
「認知症=怖いもの」と感じるかもしれませんが、
正しく知ることで、心が少し軽くなり、できることが見えてきます。
このページでは、認知症の症状や原因、予防方法などの基礎知識を、できるだけやさしく、わかりやすくご紹介します。

認知症とは?

認知症とは、脳の働きが徐々に低下し、
「ものを覚える」「判断する」「日常生活を送る」といったことに支障が出てくる状態です。
認知症の基本的な特徴
-
一時的なもの忘れとは異なり、日常生活に支障が出るレベルの記憶障害が見られます。
(例:食事をしたこと自体を覚えておらず「まだ食べていない」と何度も言う など) -
誰でもなる可能性があり、特に高齢になるほど発症リスクが高まります。
実際に、65歳以上ではおよそ7人に1人が認知症とされており、特別な病気ではなく、年齢とともに誰にでも起こりうるものです。 -
一度発症すると完全に治すことは難しいですが、早期発見と適切な対応により、進行をゆるやかにすることができます。
薬による治療や生活習慣の見直し、ご家族や周囲のサポートによって、ご本人らしい暮らしをより長く保てることがあります。
認知症のしくみと起こる変化
認知症は、脳の神経細胞に変性や障害が起こることで、情報を処理したり、覚えたり、判断したりする力が弱くなっていく病気です。
その結果、少しずつ日常生活に支障が出てくるようになります。
たとえば、
- 予定を忘れる
- 料理の手順がわからなくなる
- 場所や人がわからなくなる
といった変化が見られるようになります。
これらの変化は、決してご本人の性格のせいではありません。
脳に起きている変化が原因で、誰にでも起こりうることなのです。
仕組みを知ることで、「理解し支える」第一歩になります。

- 脳の神経細胞の
障害・変性 - 情報処理が
うまくできなくなる - 記憶・判断・理解力
などの低下 - 日常生活に支障が
出るようになる - ご本人・ご家族の
不安や困りごとが
増える
脳の中では、
なにが起きているの?
認知症は、脳の病気です。
脳内の「神経細胞(ニューロン)」が壊れてしまうことで、情報の伝達や処理がうまくいかなくなり、記憶・判断・理解などの力に影響が出てきます。
脳にはそれぞれの部位に役割があり、障害を受けた場所によって現れる症状も異なります。
| 脳の部位 | 主な働き |
|---|---|
| 海馬 | 記憶の整理・保存 (新しいことを覚える) |
| 前頭葉 | 判断・計画・感情の コントロール |
| 側頭葉 | 言葉の理解や 聞いた情報の処理 |
| 後頭葉 | 見たものの情報を処理 (視覚) |
たとえば、アルツハイマー型認知症では、海馬からダメージが始まるため、初期から記憶障害が目立ちます。
レビー小体型認知症では、幻視や体のふるえなど、他のタイプにはない特徴的な症状が見られることもあります。
神経細胞が壊れるとどうなるの?
脳の神経細胞は、電気信号や化学物質を使って互いに情報をやりとりしています。
認知症になるとこの神経細胞が壊れたり減ったりして、情報のやりとりがスムーズに行えなくなります。
その結果──
-
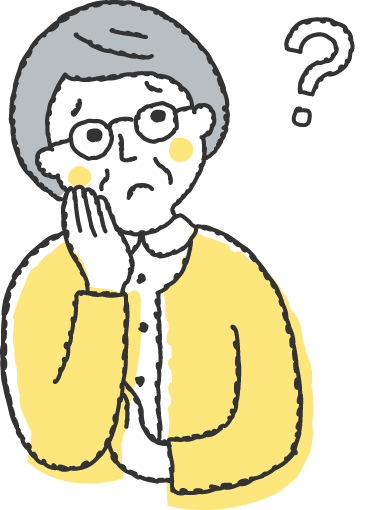
情報を覚えられない
-

判断ができない
-
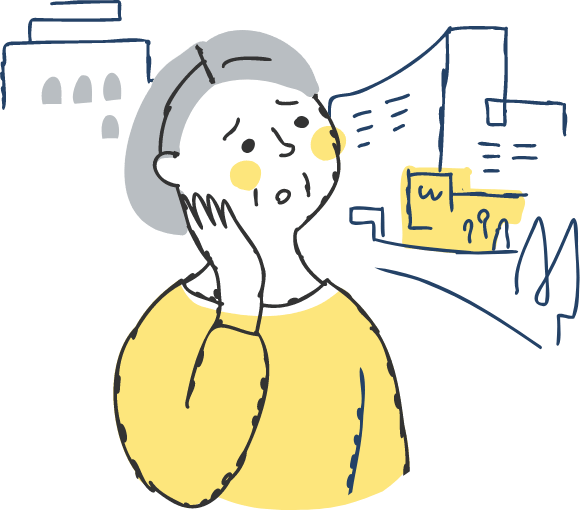
行動に支障が出る
という流れで、少しずつ日常生活に影響が広がっていきます。
| 種類 | 原因となるたんぱく質 | 主な症状の特徴 |
|---|---|---|
| アルツハイマー型 | アミロイドβ、タウ | 新しいことを覚えられない、 日付や場所がわからなくなる |
| レビー小体型 | レビー小体 | 幻視、認知の波、ふらつき、 体の動きの変化など |
たとえば、アルツハイマー型認知症では、海馬からダメージが始まるため、初期から記憶障害が目立ちます。
レビー小体型認知症では、幻視や体のふるえなど、他のタイプにはない特徴的な症状が見られることもあります。
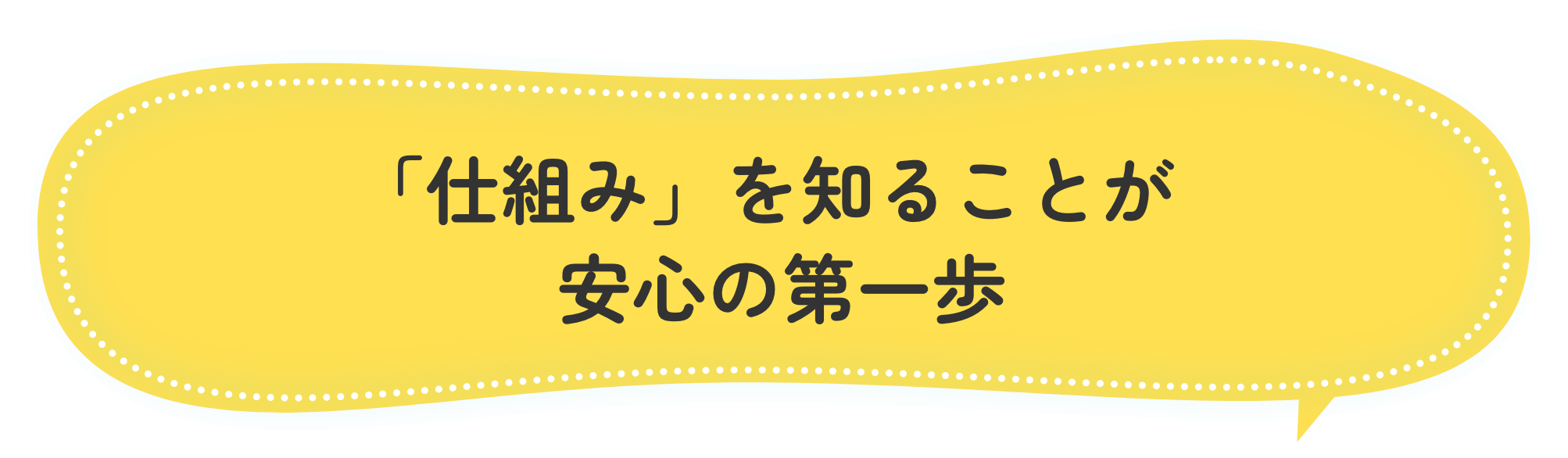
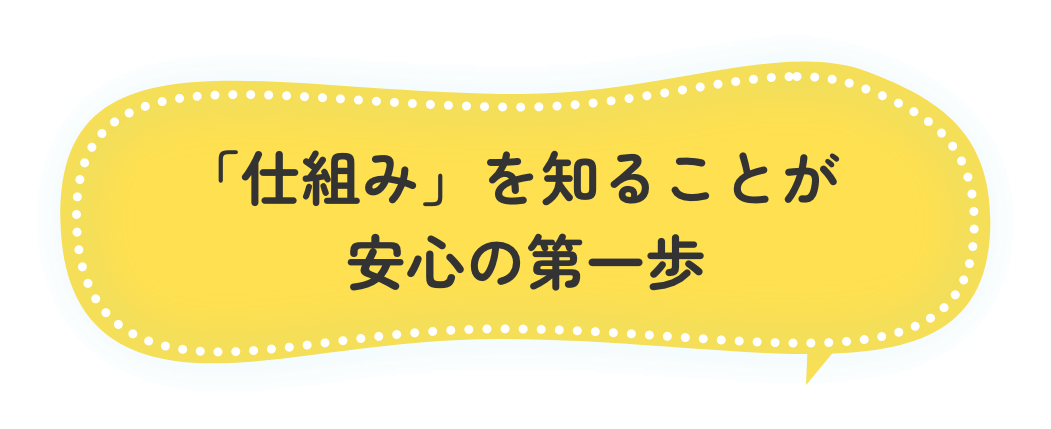
認知症は、誰にでも起こりうる脳の変化による病気です。
そのしくみを理解することで、
「年のせい」と決めつけず、
ご本人やご家族にできるサポートが見えてきます。
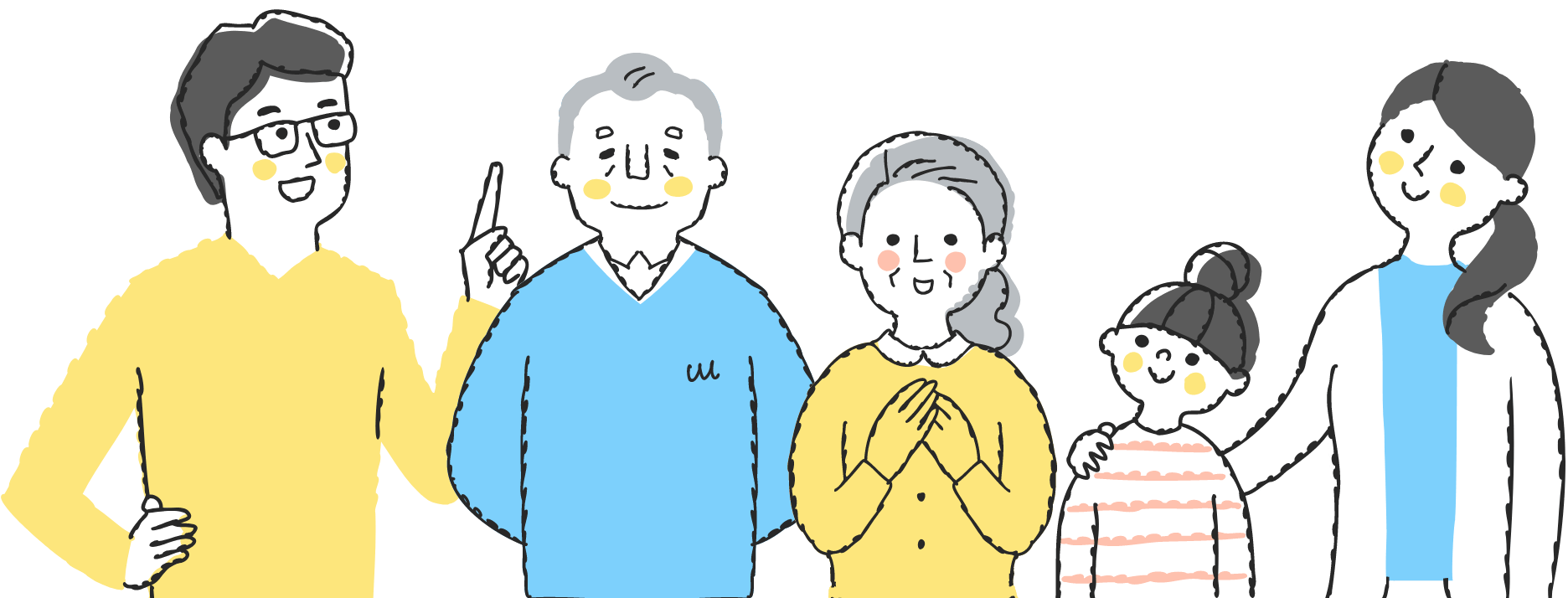
認知症の主な症状の種類
認知症の症状は、「中核症状」と「周辺症状」の2つに分けられます。
中核症状は、脳の神経細胞が障害を受けたことによって起こる、記憶・判断・理解といった基本的な機能の低下です。すべての認知症の方に共通して見られます。
一方、周辺症状(BPSD)は、ご本人の体調や住まいの環境、家族との関係などが影響して現れる行動や感情の変化です。
怒りっぽくなったり、幻覚が見えたり、夜中に動き回るなど、日によって症状が違うこともあります。
周辺症状は環境や関わり方で軽減できることもあるため、周囲の理解と工夫が大切です。
-
中核症状(脳の障害が直接原因)

- 記憶障害
出来事を忘れる - 見当識障害
時間や場所、人がわからなくなる - 判断力の低下
状況に合った行動ができない - 実行機能障害
段取りや手順がわからなくなる
- 記憶障害
-
周辺症状(環境・心理が影響)
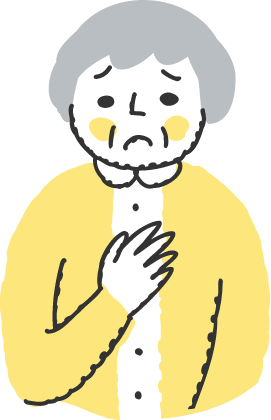
- 不安・イライラ
落ち着かない、急に怒るなど - 妄想・幻視
あり得ないことを信じる、
見えないものが見える - 徘徊・うつ状態
目的もなく歩き回る、元気がなくなる - 昼夜逆転・暴言など
夜に起きる、突然怒鳴る
- 不安・イライラ
認知症の4つの代表的なタイプと特徴
認知症にはいくつかのタイプがあり、原因や症状の現れ方が異なります。
| タイプ | 主な特徴 | 進行の速さ | 感情の変化 | 身体症状 |
|---|---|---|---|---|
| アルツハイマー型 | 最も多いタイプ。記憶障害(出来 事を忘れる)から始まり、徐々に 進行。 |
ゆっくり進行 | 感情の起伏は 比較的少ない |
特になし |
| 脳血管性 | 脳梗塞などが原因。症状にムラが あり、段階的に悪化する。 |
比較的速い/階段状 | 不安・イライラ (落ち着かない、 怒りっぽいなど) |
手足のマヒが 出ることもある |
| レビー小体型 | 幻視が出やすい。認知機能の波が 大きく、日によって状態が変わる。 |
変動が大きい | 感情の波がある、 混乱しやすい |
手足のふるえ、 歩行のふらつき |
| 前頭側頭型 | 人格や行動の変化が目立つ(反社 会的言動など)。若年発症もある。 |
比較的速い | 抑制が効かない、 怒りっぽくなることがある |
初期は少ないが 行動の異常が目立つ |
それぞれのタイプによって、進行の速さや症状のあらわれ方、感情の変化や身体への影響などに違いがあります。
ゆっくり進行するものもあれば、感情の起伏や身体のふらつきが目立つもの、行動や性格の変化が強く出るものもあります。
こうした違いを理解しておくことで、ご本人の状態に合った対応やケアがしやすくなります。
各タイプのより詳しい特徴については、こちらのページでもご紹介しています。
認知症の種類と特徴について詳しく見る加齢による「もの忘れ」との違いは?
「年齢のせいかな?」「物忘れが増えたけど大丈夫?」
そんなとき、加齢による自然な変化か、認知症の始まりなのかを見極めるのは難しいものです。
加齢による物忘れは、たとえば「昨日の夕飯のメニューが思い出せない」程度で、思い出せば「ああ、そうだった」と納得できます。
しかし、認知症では「夕飯を食べたこと自体を覚えていない」といった“体験のまるごとの消失”が起きます。
また、認知症は徐々に進行し、日常生活に明確な支障が出てくる点が大きな違いです。
早期に気づいて対応することで、進行を緩やかにしたり、ご本人が望む暮らし方を準備できる可能性があります。

| 比較項目 | 加齢による もの忘れ |
認知症の場合 |
|---|---|---|
| 忘れ方 | 体験の一部を 忘れる |
体験そのものを忘れる |
| 自覚 | 自分で 気づいている |
自覚がないことが多い |
| 進行 | あまり進まない | 徐々に進行し、症状が悪化する |
| 日常生活 への影響 |
ほとんど 支障がない |
支障をきたし、 助けが必要になることも |
予防と早期対応のポイント
認知症の進行をゆるやかにし、心豊かな生活を続けるためには、日頃の過ごし方や気づきが大切です。
予防に効果的な生活習慣
-
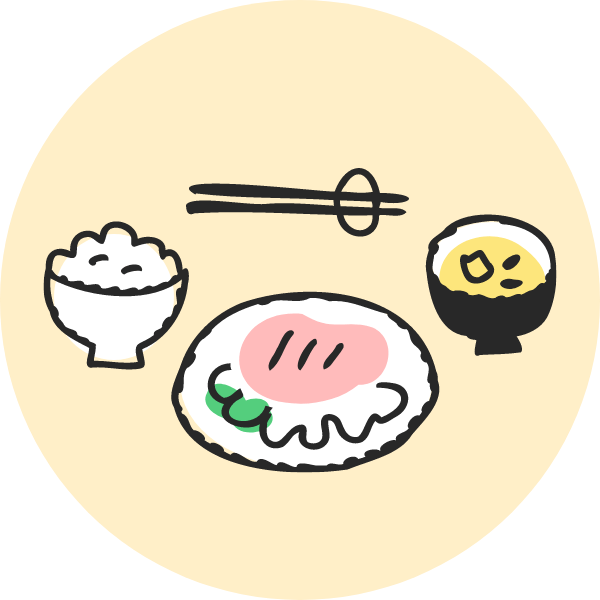
規則正しい生活と
バランスの良い食事 -
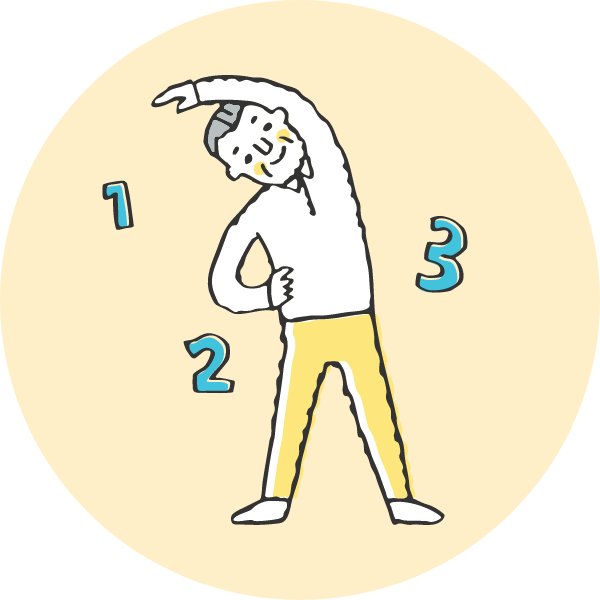
適度な運動
散歩・ストレッチなど -
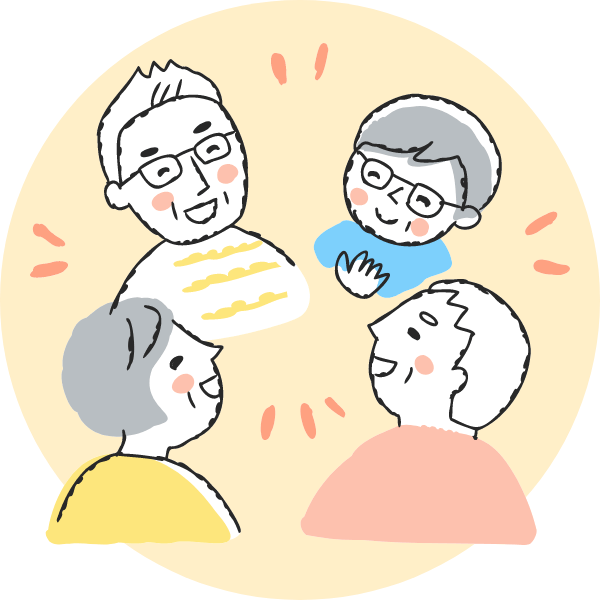
人との交流・会話
-
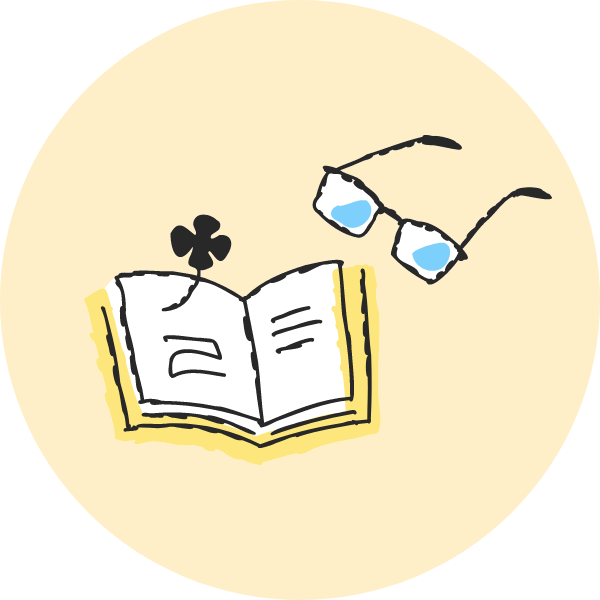
脳への刺激
読書・趣味・学び
早期発見のメリット
-

進行を抑える薬や
サポートが早く受けられる -
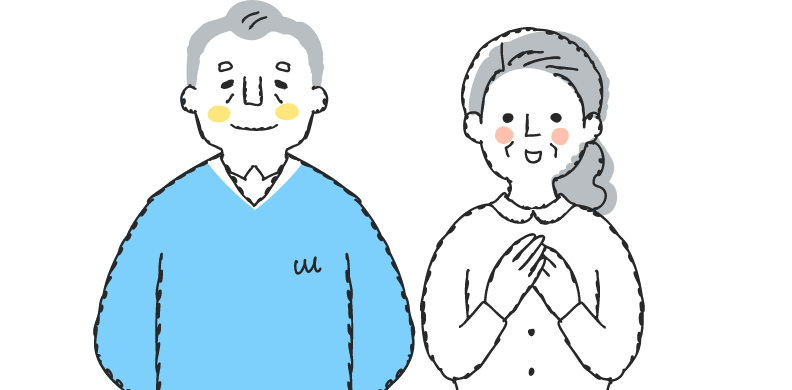
ご本人の意思を大切にした
今後の生活設計ができる -

ご家族の不安や負担が
軽くなる -

必要な情報や支援度について、
早めに知ることができる
よくあるご質問(FAQ)
Q 認知症は治せますか?
A 現在の医療では完治が難しいケースが多いですが、早期発見と治療・リハビリで進行を緩やかにできる可能性があります。
Q どの診療科に行けばいいですか?
A
「もの忘れ外来」や「神経内科」「精神科」などが対応しています。
まずはかかりつけ医に相談しても良いでしょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
Q 家族が受診を嫌がります。どうすれば?
A ご本人の気持ちに配慮しながら、「健康チェックの一環」といった形でやさしく促すのが良いと言われています。
Q 認知症の家族にどう接すればよいですか?
A 話をよく聞き、やさしい言葉で伝え、間違いを正そうとせず、その人の気持ちを大切に寄り添うことが大切です。
Q 認知症の予防にはどんな方法がありますか?
A
日常の中で頭と体を一緒に使うことが大切です。
楽しく体を動かしながら考える「認知症予防体操」などを取り入れることで、脳と体の両方にやさしい刺激を与え、心もリフレッシュできます。
Q 介護が必要になったとき、誰に相談すればよいですか?
A 介護が必要になったときは、地域包括支援センターや市区町村の介護保険課、かかりつけ医などに相談できます。
「まずは気軽に相談したい」という方には、アプリ「ベルコメンバーズ」の「介護相談ダイアル」がおすすめです。
介護サービスや施設入居、暮らしの工夫など、介護に関する不安や悩みを専門スタッフに電話で相談できます。
認知症は、誰にでも起こり得る
身近な病気です。
でも、
それは決して「何もできなくなること」
ではありません。
今できること、これからできることを、
焦らず、やさしく考えていきましょう。