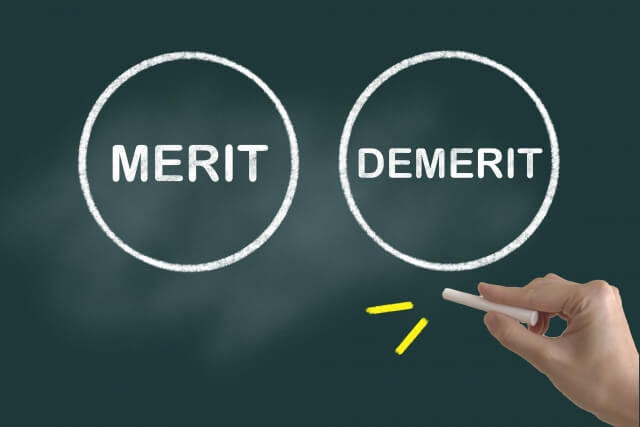介護の分野では近年、混合介護と呼ばれるスタイルが注目を集めています。
混合介護とは、「介護保険内で受けられるサービス」と「保険外サービス」を組み合わせることです。
うまく混合介護を活用すれば、利用者やご家族の負担を大きく和らげることが可能となります。
今回は、「混合介護の概要を解説」するとともに、「メリット・デメリット」についても詳しくご紹介します。
混合介護とは?

混合介護とは、介護保険が適用される公的サービスと適用されない自己負担のサービスを組み合わせて利用する仕組みです。
混合介護を利用できるようになれば、介護保険の範囲を超えた幅広いニーズに対応できます。
例えば、訪問介護で身体介護を受けながら、掃除や洗濯、ご家族の分の食事作りといった生活支援も一緒に依頼できるでしょう。
しかし、現在は保険対象のサービスと対象外のサービスを明確に区別する必要があり、同時には提供できません。
そのため、利用者は混合介護を利用しにくいのが実情です。
このような課題を受けて、政府は保険内外のサービスを柔軟に組み合わせられる「混合介護の規制緩和」について検討を進めています。
これにより、より便利で効率的な介護サービスの提供が期待されています。
なお、現時点で介護保険対象のサービスと介護保険の対象外となるサービスの例は、以下の通りです。
| 介護保険対象のサービス | 介護保険対象外のサービス |
|---|---|
|
・食事のサポート ・着替えや身体の整容のサポート ・入浴介助や清拭 ・通院や外出の付き添いサポート ・服薬介助 ・着替えの介助 ・介護を必要とする方の食事の準備や調理 ・介護を必要とする方の居室や生活スペースの掃除、整理整頓 ・介護を必要とする方の衣服の洗濯 ・日常生活に必要なものの買い出し ・薬の受け取り など |
・介護を必要とする方以外の人のための調理や洗濯、買い物 ・介護を必要とする方以外が利用する居室の掃除や整頓 ・家具の移動、電気器具の移動、修理、模様替え、大掃除 ・日用品以外の買い物 ・草むしり、草木の水やり ・ペットの世話 ・趣味の外出への付き添い ・Webカメラやセンサーカメラを使っての見守り など |
介護保険対象外のサービスは、全額自費で依頼する必要があります。
さまざまなサポートを申し込んだ場合、料金が高額になってしまう恐れもあるため、注意しましょう。
これから老人ホームを探そうとお考えなら、こちらの記事も参考にしてみてください。
『老人ホームの選び方と失敗しないための10のポイント』
⇒ ご参照ください。
混合介護のメリット

混合介護の規制緩和が進めば、介護サービス利用者だけでなく、そのご家族、介護事業者にも良い影響をもたらすと考えられます。
ここからは、「混合介護を利用するメリット」について順を追って紹介していきます。
1. 充実したサービスを受けられる
介護保険内で受けられないサービスを利用できるようになるのが、混合介護のメリットの一つです。
これまでの居宅介護では、同居するご家族に対するサポート、ペットの世話や大掃除といった介護保険外のサポートを受けられませんでした。
居宅介護はあくまで、介護を必要とするご本人を対象としたサービスとされているためです。
混合介護の利用によって、既存の枠にとらわれず、充実したサービスを受けやすくなることが期待できます。
2. ご家族の負担が軽減し、介護環境が向上する
混合介護の大きなメリットは、ご家族の負担を軽減できる点にあります。
介護保険の範囲内で受けられるサービスは限られるため、ご家族に負担がかかるかもしれません。
例えば、介護を必要とする方の食事作りや買い出しのみをサポートしてもらった場合、同居するご家族はご本人の分とは別に食事を用意する必要があります。
このようなケースでは、「介護サービスを受けると、かえって手間がかかる」と、ご家族が不便を感じる恐れがあります。
しかし、混合介護の利用によって同居するご家族の分の食事作りも依頼できるようになれば、ご家族の負担は大きく軽減するでしょう。
また、幅広いサポートを利用しやすくなるため、ご家族の介護環境の向上にもつながります。
3. 介護事業所の収益がアップしやすくなる
混合介護は、介護サービス事業者側にも大きなメリットをもたらします。
これまで提供できなかったサービスを別料金で提供できれば、介護サービス事業所の収益が大きく高まります。
介護事業所の収益がアップすれば、介護職員の待遇改善も見込めるでしょう。
混合介護の利用者増加をきっかけとした介護事業者間の競争は、サービスの質の向上にもつながります。
介護業界全体が活性化すれば、利用者がより手厚いサービスを受けられるようになる可能性もあります。
混合介護のデメリット

混合介護には多くのメリットがありますが、一方で、いくつかのデメリットも考えられます。
ここからは、「混合介護のデメリット」を紹介します。
メリットと比較しながら、混合介護が自身に合うかどうかを検討してみると良いでしょう。
1. 介護サービス利用者の費用負担が増える
混合介護のデメリットの一つは、利用者の費用負担が増えることです。
介護保険が適用されるサービスのみを利用した場合、利用者の費用負担は1~3割ほどに抑えられます。
しかし、介護保険適用外のサービスを利用する場合には、全額を自費でまかなわなければなりません。
10割負担のサービスを利用した場合、費用負担は大きく増えます。
2. 高額のサービスが提供される恐れがある
介護保険外のサービスには現状、料金設定の規制がありません。
業者によっては、相場よりもかなり高い金額でサービスを提供することもあるでしょう。
混合介護を利用するに当たって、料金を確認しないまま介護保険適用外サービスを申し込むと、思わぬ金額を請求されるかもしれません。
もちろん、混合介護を利用できる施設が増えれば、事業者同士の公正な競争が生まれやすくなり、適正価格でサービスが提供される可能性は高まります。
しかし、かなり高い価格でサービスが提供されるケースも十分考えられるため、注意しましょう。
3. 不要なサービスを契約してしまうことがある
混合介護を検討する高齢者の中には、認知機能の低下によって自己判断や意思決定が難しい方もいます。
判断能力が低下した状態で、介護保険内のサービスと保険外サービスを選択するのは、かなり難しいでしょう。
高齢者が押し売りのような形で混合介護を勧められ、後から高額な支払いを求められるケースもあるかもしれません。
混合介護を利用する際には、どのようなサービスを利用するかを十分に見極めることが大切です。
また、ご家族などの身近な方がサービス内容をチェックするのも有効な対策となるでしょう。
4. 利用者の自立が阻害される恐れがある
混合介護は便利な反面、利用者の自立を妨げる恐れもあります。
例えば、家事代行サービスは利用者の生活を楽にする一方で、ヘルパーが全てを代行すると、ご本人が自分で体を動かす機会を失ってしまうかもしれません。
特に、食事や着替え、入浴などの日常生活動作を過剰にサポートすると、本来できるはずのことができなくなる可能性があります。
厚生労働省は、介護保険制度の基本理念である「自立支援」と「重度化防止」の観点から、保険外サービスを組み合わせる際は、利用者の状況に応じて適切な支援の程度を見極めることが重要だと指摘しています。
従って、混合介護を利用する際も「介護はあくまでも利用者自身の自立支援である」という視点が重要です。
混合介護を提供する事業所をお探しなら、「あなたらしく」をご活用ください。