認知症の高齢者がグループホームに入居すると、入居一時金や保証金といった初期費用の他、月額費用として介護サービス費やその他の生活費が発生します。
このうち、「介護サービス費用」は公的介護保険の適用対象となりますが、具体的にどのくらいの費用がかかるのでしょうか?
今回はグループホームの費用相場とその内訳、利用する際の自己負担額、入居費用の軽減につながる制度について解説します。
【料金一覧表】グループホームの費用相場と内訳

グループホームの費用は、大きく分けると「初期費用」と「月額費用」の2つです。
初期費用は入居時に一度だけ支払い、月額費用は入居している間、毎月支払います。
どちらも費用は施設によって異なりますが、ここではグループホームの一般的な費用相場と、それぞれの内訳について解説します。
初期費用の相場と内訳

初期費用は、主に入居一時金と保証金の2つで構成されます。
「入居一時金」とは、そのグループホームを利用する権利を取得するためにかかる費用です。
施設によって、入居申込金、施設協力金など名称が異なる場合があります。
一般的な賃貸住宅の前払い家賃にあたるもので、多くの施設では入居一時金の一部を初期償却として扱い、残りを一定期間内で償却するという仕組みです。
そのため、一定期間内にグループホームを退去した場合、未償却の入居一時金が利用者に返還されるところもあります。
ただ、入居一時金には国が定めた明確な基準がなく、金額をはじめ、償却期間や償却率は施設によって大きく異なるため、入居一時金なしで入居できるグループホームもあれば、入居時に百万円単位の費用が必要になるところもあります。
入居一時金の全国平均は「10万円程度」とされていますが、実際に入居する際は必ず事前に詳しい入居一時金の額を確認しましょう。
一方の「保証金」は、利用者が退去する際にかかる修繕費や、利用料を滞納した際の充填などに利用される費用です。
賃貸住宅の敷金にあたり、グループホームを退去する際は、修繕費や充填費などを差し引いた額が返金されるのが一般的です。
保証金も入居一時金同様、国が定めた明確な基準がないため、施設によって金額に差があります。
厚生労働省が公開している「高齢者向け住まいの実態調査 報告書」によると、介護付有料老人ホームや住宅型有料老人ホームといった高齢者向け住まい全体の入居時にかかった保証金の全国統計は「約11万6,000円」です。(※注1)
なお、グループホームによっては入居一時金と保証金を区別していなかったり、入居一時金なしで保証金のみ請求したりするところもあります。
月額費用の相場と内訳

グループホームの月額費用は「介護サービス費」と「生活費」、「サービス加算」の3つに区分されます。
「介護サービス費」とは、介護サービスを受けるためにかかる費用です。
介護サービス費、ユニット(入居者で構成される小グループ)の数、利用者の要介護度によって異なります。
要介護度が高いほど介護サービス費も高くなる傾向にあり、1ユニットの施設の月額料金の目安は以下のようになっています。
| 要介護度 | 介護サービス費の目安 |
|---|---|
| 要支援2 | 約22,800円 |
| 要介護1 | 約22,900円 |
| 要介護2 | 約24,000円 |
| 要介護3 | 約24,700円 |
| 要介護4 | 約25,200円 |
| 要介護5 | 約25,700円 |
かなりの高額ですが、介護サービス費は公的介護保険の適用対象となるため、負担割合は「1~3割程度」で済みます。
一方の「生活費」は、グループホームで生活するにあたって必要となる介護サービス費以外の費用です。
具体的には、賃料や管理費、食費、水道光熱費などがこれに該当します。
生活費は施設によって差が大きいですが、費用相場は「月額約12万円」とされています。
具体的な内訳は以下のとおりです。
| 生活費の内訳 | 月額費用の目安 |
|---|---|
| 賃料 | 5~6万円程度 |
| 共益費・管理費 | 5,000円~7,000円程度 |
| 食費 | 3~4万円程度 |
| 水道光熱費 | 1万~1万5,000円程度 |
これらはグループホームで生活するにあたって必要不可欠な費用ですが、公的介護保険の適用対象外であるため、利用者が実費で負担しなければなりません。
また、上記の費用以外にも、理美容代やおむつ代、通信費、新聞購読費、レクリエーション参加費、定期健康診断費、医療費や薬剤費などがかかる場合もあります。
最後の「サービス加算」とは、より質の高い介護サービスを受けるために要する費用で、正式名称をサービス提供体制強化加算といいます。
サービス加算の算定の対象となる介護サービスは介護報酬改定によって定められており、グループホームでは全スタッフ数に占める専門職(介護福祉士等)の割合や、専門職の勤続年数、常勤職員の割合の他、夜間支援体制が整っているか、若年性認知症の利用者を受け入れているか、看取り介護を行っているかなどの要件によって加算や減算が決まります。
サービス加算が高いほど質の高いサービスを期待できますが、その分月額費用は上乗せされます。
要件1つあたりのサービス加算の額は、1日あたり「数円~数十円程度」と少なめですが、複数のサービス加算が重なっている場合、毎月の加算が数千円~数万円に及ぶこともあります。
月額費用を確認する際は、必ずサービス加算についても問い合わせておきましょう。
グループホームを利用するときの自己負担額

上記でグループホームの一般的な費用相場を説明しましたが、このうち介護サービス費とサービス加算は公的介護保険の適用対象です。
介護保険が適用されると、介護サービス費およびサービス加算は原則として1割負担となり、介護サービスを受ける際の自己負担額が大幅に減少します。
ただ、利用者の所得によっては負担割合が2割または3割になる場合があります。(※注2)
仮に介護サービス費とサービス加算の合計額が月に26万円だった場合、1割負担なら2万6,000円、2割負担なら5万2,000円、3割負担なら7万8,000円です。
生活費の負担は月々11万円~12万円が相場ですので、合計すると約14万円~20万円程度が月額費用の相場となります。
なお、入居一時金や保証金も公的介護保険の適用対象外ですので、費用は全て自己負担となります。
グループホームの入居費用軽減につながる制度

国や自治体では、グループホームの入居費用を軽減するための制度を設けています。
ここではグループホームの入居費軽減につながる制度を「4つ」ご紹介します。
高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、1カ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えた際、超過した分が払い戻される制度です。(※注3)
基準となる負担限度額は利用者の所得によって以下のようになっています。
| 基準要件 | 負担限度額 |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 14万100円 |
| 課税所得380万円~690万円未満 | 93,000円 |
| 市町村民税課税~課税所得380万円未満 | 44,400円 |
| 世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の場合、個人の負担上限額は15,000円) |
| 生活保護を受給 | 15,000円 |
なお、これらは公的介護保険の対象となるサービスのみで、生活費などは対象外です。
[注3]厚生労働省.「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」
自治体の助成金
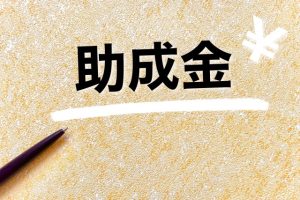
国の制度とは別に、自治体が独自に助成金制度を設けているケースもあります。
助成の内容はさまざまで、介護サービス費の自己負担割合が軽減されるところもあれば、公的介護保険の適用対象外となる生活費を一定額まで助成するところもあります。
助成金の有無や適用条件は自治体によって異なりますので、お住まいの市区町村役場に問い合わせてみましょう。
特定障害者特別給付費(補足給付)

特定障害者特別給付費(補足給付)とは、グループホームなどに代表される障害福祉サービスにかかる支給決定を受けた障害者のうち、所得など一定要件を満たす場合に食費や賃料などにあてられる給付金を支給する制度です。(※注4)
特定障害者特別給付費は国が定め、自治体によって行われる助成制度ですが、制度の導入は義務ではないため、自治体によって給付の有無は異なります。
[注4]愛媛県.「介護給付費等に係る支給決定事務等について」p2,p3.
社会福祉法人の軽減制度

グループホームを運営しているのが社会福祉法人である場合、低所得者向けに自己負担軽減制度を実施しているところもあります。
要件を満たせば介護保険サービス費の自己負担額や生活費が軽減される可能性がありますので、施設の担当者に問い合わせてみましょう。
【まとめ】高齢者が入居するグループホームの費用は施設によって大きく異なる
グループホームの費用は、「初期費用」と「月額費用」の2つに区分されますが、いずれも施設によって金額に大きな差があります。
介護サービス費用とサービス加算には公的介護保険が適用されますが、それ以外の入居一時金や保証金、生活費には保険が適用されません。
グループホームは一度入居したら長く利用するのが一般的ですので、家計の大きな負担にならないよう、各施設の利用料金はしっかり下調べしておきましょう。
施設ごとの料金や特徴を調べたいときは、「あなたらしく」の利用をおすすめします。










