厚生労働省の「生活保護の被保護者調査(令和5年5月分)」によると、生活保護を受給している世帯のうち、55.6%が高齢者世帯です。[注1]
高齢や障害によって働けなくなったり、年金だけでは暮らしていけなくなったりして、生活保護を受給する方が少なくありません。
高齢者が生活保護を受ける場合、介護保険料は自費になるのでしょうか。
本記事では、生活保護の受給者が介護サービスを受けた場合の「自己負担額」についても詳しく解説します。
[注1] 厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和5年5月分)」P1 第2節 2)」
高齢者が生活保護を受けるための条件

厚生労働省のホームページによると、高齢者が生活保護を受けるための条件は「4つ」あります。[注2]
| 資産の活用 | 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。 |
| 能力の活用 | 働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。 |
| あらゆるものの活用 | 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。 |
| 扶養義務者の扶養 | 親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。 |
1. 資産の活用

高齢者の方でも、生活費に充てられる資産をお持ちの場合、生活保護が認められない場合があります。
例えば、資産の例として、預貯金や土地・家屋の他、生命保険金、自動車などが該当します。
2. 能力の活用

身体状況的に働くことが可能な場合は、シルバー人材センターや高齢者向けの求人を活用し、可能な限り収入を得る必要があります。
要支援や要介護の認定を受けている場合など、働くことが難しい場合はその限りではありません。
3. あらゆるものの活用

生活保護制度の他にも、年金や児童扶養手当など、他の制度で給付を受けられる場合があります。
生活保護を受ける前に、あらゆる制度を活用して収入を確保する必要があります。
4. 扶養義務者の扶養

子や兄弟姉妹、親戚などが存命中の場合、生活保護ではなく親戚の援助を受ける必要があります。
なお、生活保護法における「扶養義務者」とは、本人から見て3親等までの親族です。
例えば、甥や姪、曾孫なども扶養義務者に含まれます。
高齢者が生活保護を受けている場合の介護保険料・自己負担額

通常、介護保険料の支払いは40歳から発生します。
高齢者が生活保護を受けている場合、介護保険料の支払いは発生するのでしょうか。
また、介護サービスを利用する場合の自己負担額はいくらでしょうか。
結論からいうと、生活保護を受けている方は、介護保険料や介護費用を自分で負担する必要はありません。
40歳から65歳までの受給者の場合は、介護保険上の第2号被保険者ではなく、「みなし2号」という扱いになります。
そのため、介護保険料の支払いは発生しません。
ただし、介護保険における特定疾病に罹患した場合は、要介護認定の審査を受け、第2号被保険者と同様に介護サービスを利用することが可能です。
この場合、介護費用の全額が介護扶助の名目で支給されるため、受給者の金銭負担はありません。
一方、65歳以上の受給者の場合、介護保険に加入する必要があります。
そのため、介護保険料の支払いが発生しますが、介護保険料の全額が生活扶助の名目で支給されます。
生活扶助は生活保護費に上乗せされる形で支給されるため、実質的な金銭負担はありません。
ただし、「介護保険料に係る生活保護受給者の取扱いについて」の通知のとおり、自治体が生活扶助の金額を決定するため、受給者は介護保険に関する情報を速やかに提供する必要があります。[注3]
生活保護制度において、第1号被保険者の介護保険料については、普通徴収の場合は、生活扶助の介護保険料加算として実費を支給、また、特別徴収の場合は、収入認定において年金収入からの控除をすることとされています。
そのため、扶助額の適正な決定を速やかに行えるよう、保険者は保護の実施機関に対して被保護者の保険料額等の情報の連絡が必要です。
また、65歳以上の受給者が要介護認定を受けた場合、介護費用の全額が介護扶助の名目で支給されます。
介護が必要になったら、ケアプランナーが作成した「ケアプラン」を生活保護の窓口に提出しましょう。
[注3] 厚生労働省「介護保険料に係る生活保護受給者の取扱いについて」
高齢者が生活保護を受けるメリット・デメリット
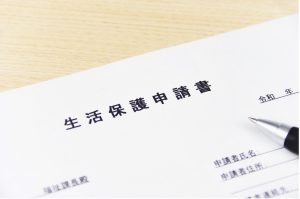
高齢者が生活保護を受けるメリットやデメリットは以下のとおりです。
| メリット | ・生活保護費が支給される ・税金や保険料の支払いが免除される |
| デメリット | ・利用できない老人ホームもある |
1. 保護費が支給される

生活保護を受給すれば、厚生労働大臣が定めた基準に基づいて、一定の生活保護費が支給されます。
生活保護費の金額は、生活に必要な「最低生活費」から、受給者の収入を差し引いた差額です。
この収入には、年金や児童扶養手当の他、就労による収入や親族の援助なども含まれます。
生活保護費は、最低限度の生活を営むための扶助に過ぎず、決して多い金額ではありません。
しかし、収入の手立てがなく、生活が苦しい高齢者にとっては貴重な収入源になります。
2. 税金や保険料の支払いが免除される

また、生活保護の受給者は、税金や保険料の支払いが免除されます。
以下は免除される項目の一例です。
- 医療費
- 介護保険料
- 住民税
- 所得税
- 固定資産税
- 国民年金保険料
- 国民健康保険料
- 介護費用
- NHKの受信料
- 水道料金
- 交通費
- 子どもの保育費
ただし、自治体によっては、免除されない項目もあります。
また、支払いを免除するために申請手続きが必要な項目もあるため、自治体のホームページを確認してください。
3. 利用できない老人ホームもある

老人ホームによっては、生活保護の受給者の受け入れを行っていなかったり、入居審査に落ちてしまったりする場合があります。
生活保護を受給すれば、介護保険料や介護費用の自己負担がなくなりますが、介護サービスの支給限度額を超える金額の扶助を受けることはできません。
例えば、要介護1の方は1カ月につき「16万7,650円まで」、要介護2の方は1カ月につき「19万7,050円まで」しか介護サービスを利用できません。[注4]
| 要支援1 | 5万320円 |
| 要支援2 | 10万5,310円 |
| 要介護1 | 16万7,650円 |
| 要介護2 | 19万7,050円 |
| 要介護3 | 27万,480円 |
| 要介護4 | 30万9,380円 |
| 要介護5 | 36万2,170円 |
そのため、介護費用が高額な老人ホームの場合、入居が認められない可能性があります。
老人ホームに入居する場合は、生活保護の扶助の限度内でサービスを利用できる施設を探しましょう。
【まとめ】生活保護と介護保険料や介護費用の関係を知ろう
高齢者で生活保護を受けている方は、介護保険料や介護費用の負担について正しい知識を持っておきましょう。
原則として、介護保険料や介護費用は生活保護費から扶助されるため、受給者の金銭的な負担はありません。
ただし、生活保護の受給者の受け入れを行っていない老人ホームもあるため、施設選びに苦労する方もいます。
老人ホーム探しを始めるのなら、「あなたらしく」のご利用がおすすめです。










