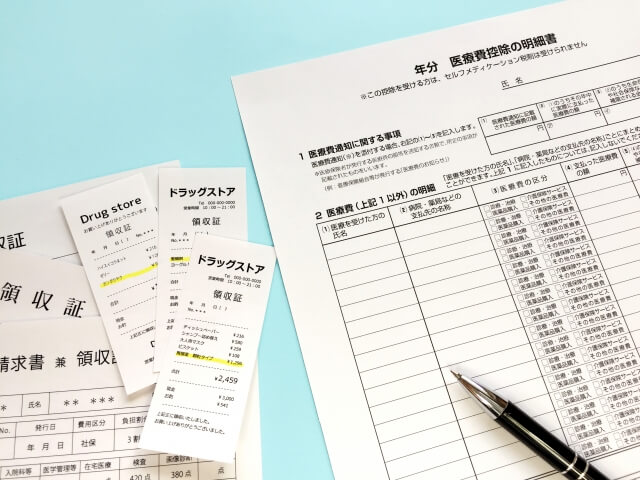老人ホームに入居した後は、施設でかかる費用のうち、食費や居住費などの施設サービス費が経済的負担となることが少なくありません。
施設サービス費を減らすことは難しいですが、一部の施設では施設サービス費が医療費控除の対象となる場合があります。
申請すれば、所得税から控除が受けられる場合があるため、老人ホーム入居による経済的な負担を軽減できる可能性があります。
今回は、老人ホームの費用の中で「医療費控除の対象となる費用」を紹介するとともに、「医療費控除の申請方法」についても詳しく解説します。
ぜひ参考にして、お得な制度を利用してみてください。
老人ホームの費用は医療費控除の対象?

老人ホームの費用の中には、一部の施設の施設サービス費(食費・介護費・居住費)やおむつ代など、医療費控除の対象となるものがあります。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に、自分や生計を共にする配偶者やその他の家族のために、一定額以上の医療費を支払った場合に、支払った医療費に応じて所得控除を受けられる制度です。
一定額以上の医療費とは、所得金額が200万円以上の場合は医療費が10万円を超えたとき、所得金額が200万円未満の場合は医療費が所得金額の5%を超えた場合を言います。[注1]
医療費控除の還付は、自分が支払った(源泉徴収された)所得税から控除を受けられるものなので、所得税が課税(源泉徴収)されていない方は、医療費控除を受けられません。
例えば、所得が年金だけの場合でも、年金受取額が一定額以上で所得税が源泉徴収されていれば、医療費控除を申請することで税金の還付を受けられる場合があります。
ただし、年金受取額が少なく年金から所得税が源泉徴収されていない場合は、医療費控除を受けられないため注意しましょう。
>>[注1]国税庁 「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
医療費控除の対象となる費用・ならない費用

老人ホームでかかる費用の中で、「医療費控除の対象となる費用と、ならない費用」を紹介します。
公的機関が運営する施設の施設サービス費は医療費控除の対象
公的機関が運営する特別養護老人ホームなどの施設サービス費のうち、自己負担額として支払った金額が医療費控除の対象となります。
一方、有料老人ホームなどの施設では、施設サービス費は控除の対象とはなりません。
| 施設サービス費が 医療費控除の対象となる施設 |
施設サービス費が 医療費控除の対象外の施設 |
|---|---|
|
・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・介護医療院 |
・介護付き有料老人ホーム ・住宅型有料老人ホーム ・サービス付き高齢者向け住宅 ・認知症高齢者グループホーム ・ケアハウス |
特別養護老人ホームの場合、医療費控除の対象となるのは、施設サービス費のうち、自己負担額として支払った金額の2分の1相当額です。
一方、介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院では、施設サービス費のうち自己負担額として支払った金額が、医療費控除の対象となります。[注1]
特別養護老人ホームは、所得税法上、病院または診療所に準ずる施設として位置づけられています。
また、介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院は、医療法上は病院や診療所には該当しませんが、医療法以外の規定では原則として病院または診療所に含まれるとされています。
そのため、これらの施設の施設サービス費も医療費控除の対象となるのです。[注1]
対して、民間企業が運営する有料老人ホームは、住居またはサービスという位置づけのため、施設サービス費は医療費控除の対象外となります。
>>[注1]国税庁 「No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」
おむつ代や外部の医療機関での受診代は医療費控除の対象
施設サービス費以外に医療費控除の対象となるのは、おむつ代や外部の医療機関での受診代などです。
ただし、おむつ代はそのままでは医療費控除の対象となりません。
おむつ代が控除の対象となるためには、寝たきりの期間が6カ月以上続いており、医師から医療行為に必要と認められて、おむつ使用証明書を発行してもらう必要があります。
有料老人ホームなどの施設では、施設サービス費が控除対象外となっても、おむつ使用証明書を発行してもらえれば、おむつ代は控除対象となります。
その他にも、下記のものが医療費控除の対象です。
有料老人ホームに入居している場合も同様です。
- 個室の使用が診療・治療に必要である場合の個室使用料(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院のみ)
- 医療機関での受診代・薬代
- 医療機関へ通院したときの交通費(公共交通機関を利用した場合)
- 訪問看護などの一部のサービス
日常生活費や特別サービス費などは医療費控除の対象外
医療費控除の対象外となるのは、施設で支払った日常生活費や特別サービス費などです。
日常生活費とは、歯ブラシやシャンプーの購入代、理髪代、被服代などの通常の生活で必要となるもので、入所者が負担することが適当と認められるものです。
また、特別サービス費とはレクリエーションなどにかかる費用で、娯楽費用となるため控除対象外となります。
その他、外部の医療機関へ通院するときに、自家用車を使った場合のガソリン代や駐車場代も、医療費控除の対象外です。
医療費控除の申請方法

会社員の場合、会社の年末調整によって正しい所得税額が計算され、税務署への申告も会社が行うため、一部の場合を除いて確定申告の必要はありません。
また、年金生活者の場合でも、公的年金などの収入が400万円以下で、公的年金以外に副業などで所得がある場合は20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。[注1]
ただし、いずれの場合も医療費控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
ここからは、「医療費控除の申請方法」を見ていきましょう。
>>[注1]政府広報オンライン 「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
医療費の領収書や明細書を保管しておく
1月1日から12月31日までに支払った医療費の領収書を保管しておきましょう。
確定申告に必要な書類の記入時に、参考にするためです。
領収書とは、老人ホームから発行される領収書、病院や薬局の領収書などです。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などで発行される領収書には、医療費控除の対象となる金額が記載されています。
また、医療機関へ公共交通機関を利用して通院した場合の交通費も医療費控除の対象ですが、交通費の領収書は入手が難しい場合もあるでしょう。
その際は、公共交通機関を利用した日、かかった金額、利用した目的、利用した人数などをメモしておけば、メモが領収書代わりになります。
なお、領収書は、確定申告が終わっても「5年間」は保存しておきましょう。
場合によっては、確定申告に必要な書類の内容を確認するため、領収書の提出が求められることがあるためです。
確定申告に必要な書類を準備する
確定申告に必要な書類には、次のようなものがあります。
- 医療費控除の明細書
- 確定申告書
- おむつ使用証明書
- 医療通知書
- 本人確認書類
医療費控除の明細書は、受診した医療機関名や医療費控除額などを記載する書類です。
保管しておいた領収書や医療通知書を参考に、記入します。
確定申告書を記入する際は、源泉徴収票に記載されている内容を記入する必要があるため、手元に用意しておきましょう。
医療費控除の明細書と確定申告書は、税務署の窓口で入手するか、国税庁のWebサイトからダウンロードすれば、入手が可能です。
おむつ使用証明書がある場合は、確定申告書に添付するか提示する必要があります。
本人確認書類は、マイナンバーカードの写しを利用します。
マイナンバーカードがなければ、マイナンバーが記載されている住民票などの書類の写しと、運転免許証やパスポートなどの写しを用意しましょう。
確定申告を行う
必要書類をまとめて税務署に提出し、確定申告を行います。
確定申告の期限は原則として、翌年2月16日から3月15日までです(土日祝日の場合は、翌週平日に繰越し)。
なお、源泉徴収によって本来支払うべき税金より多く納めていた場合は、確定申告をすることで税金が戻って来る「還付申告」ができます。
「還付申告」は、翌年1月1日から5年以内であれば申告が可能です。
確定申告には、税務署の窓口に提出する方法以外にも、郵送で税務署へ提出する方法や、e-Taxによる申告方法もあります。
自分に合った方法で申告を行いましょう。
医療費控除の対象となる老人ホームをお探しの方は、「あなたらしく」をご活用ください。