成年後見人とは、認知症などで判断能力が衰えた方に代わって、財産管理や老人ホームの入居手続きなどの法律行為を行ってくれる代理人です。
成年後見人は一人で契約や手続きを行うのが不安な方に寄り添い、本人の意見を大切にしながらサポートを行ってくれるため、身近に頼れる方がいない場合は安心して生活ができるでしょう。
しかし、成年後見人を立てる手続きは、費用や時間がかかるなどのデメリットもあります。
今回は成年後見人とは何か、必要となるケースや利用するときの注意点を詳しく解説します。
成年後見人のメリット・デメリットを知り、利用するときの参考にしてください。
※2025-06-13時点の情報です。制度の詳細については、最新情報をご確認ください。
成年後見人とは?

成年後見人とは、認知症などで一人で判断するのが難しくなった方の財産管理や、生活・医療・介護に関わる手続きなどを本人に代わって行う代理人のことで、成年後見制度によって選ばれます。
成年後見制度は、判断能力が衰えた方(被後見人)を法的に保護し支援する制度です。
判断能力が衰えた方は、悪質商法の被害や詐欺に遭うリスクが高くなります。
そのようなリスクを防ぐために成年後見人という代理人を立てて、代わりに契約や手続きを行ってもらいます。
制度には任意後見制度と法定後見制度の2つがある
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の「2つ」があります。[注1]
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 任意後見制度 | 自分で成年後見人となる人を選び、その人に支援してもらいたいことをあらかじめ決めておく制度 |
| 法定後見制度 | 被後見人の判断能力が衰えたときに、裁判所が選んだ成年後見人に支援をしてもらう制度 |
任意後見制度とは、認知症などになる場合に備えてあらかじめ自分が代理人(任意後見人)を選び、財産や不動産をどのように管理・活用してほしいかなどを契約で決めておく制度です。
任意後見制度は契約した直後から効力を発揮するわけではなく、本人(被後見人)の判断能力が衰えてきたときに、所定の手続きをすることで効力を発揮します。
法定後見制度とは、認知症などで判断能力が衰えたときに本人や親族などが家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が選んだ成年後見人(法定後見人)が被後見人を支援する制度です。
被後見人の状態によって、補助・保佐・後見の「3つの種類」があり、選ばれる後見人はそれぞれ補助人・保佐人・成年後見人と呼ばれます。[注2]
- 補助:判断能力が不十分な状態の人
- 保佐:判断能力が著しく不十分な人
- 後見:判断能力が欠けている状態が日常化している人
>>[注2]法務省 「Q3~Q15「法定後見制度について」」
成年後見人の仕事は財産管理や法律行為
成年後見人ができるのは、被後見人の財産管理や法律行為の代行です。
他にも、法定後見人だけができる行為に、契約の取り消しがあります。
例えば、認知症の方が必要のないリフォーム工事を契約したとき、成年後見人が取り消せます。
ただし、日用品(食品や衣類など)の購入など日常生活に関する行為は、法定後見人であっても取り消しはできません。
| 成年後見人ができること | 成年後見人ができないこと |
|---|---|
|
・通帳などの保管 ・年金などの収入の把握や管理 ・生活費、医療費、税金などの支払い ・不動産の維持管理や売却(居住用不動産は家庭裁判所の許可が必要) ・遺産相続手続き ・医療機関の受診、入院手続き ・介護保険の申請、介護サービス利用開始の手続き ・施設入居の契約 ・被後見人が行った契約の取り消し(法定後見人のみ可能) |
・被後見人の食事の世話 ・被後見人の家の掃除 ・介護 ・話し相手 ・手術をするかどうかなど、治療方針への同意 ・日用品の購入を取り消すこと ・身元引受人(身元保証人、連帯保証人)になること ・葬儀や火葬などの死後に関わること |
成年後見人になれるのは親族や専門職などさまざま
成年後見人になれるのは、親族をはじめとする次のような人や団体です。
- 親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹・その他の親族)
- 専門職(社会福祉士・司法書士・弁護士など)
- 市民後見人(専門職でも親族でもない市民)
- 法人後見(社会福祉法人・社団法人・NPO法人などの法人)
任意後見制度の場合は、被後見人が成年後見人になる人をあらかじめ決められます。
一方、法定後見制度では家庭裁判所が成年後見人になれる人の中から、被後見人にとって適任と思われる人を選びます。
申立時に後見人の候補者を挙げられますが、親族を希望したからといって希望した人がなれるわけではありません。
被後見人に法律上や財産管理上の課題があるときは、弁護士や社会福祉士などの専門職が選ばれる場合があります。
成年後見人が必要となるケース
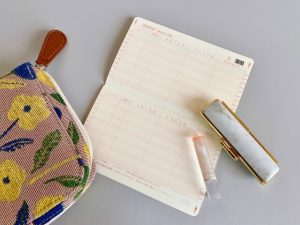
成年後見人が必要となるケースには、次のようなものがあります。
銀行口座が凍結されてしまったとき
認知症の方の銀行口座が凍結されてしまった場合、凍結の解除に成年後見人が必要です。
口座凍結は認知症の人が誤った契約をしたり、詐欺被害に遭わないようにしたりする目的で行われます。
家族が金融機関で口座を持っている本人が認知症であることを話したときや、金融機関窓口での本人の言動によって認知症と金融機関に判断されると、口座の凍結が起こる場合があるため注意しましょう。
口座が凍結されてしまうと、口座の解約や預貯金の引き出しができなくなります。
そのため、介護される方の年金などを介護費用に使いたくても口座から預金を引き出せず、家族が自分の財産から負担する必要があるかもしれません。
口座が凍結されてしまった場合は、法定後見制度を利用して成年後見人を立てて、解除してもらう必要があります。
ただし、成年後見人が選ばれるまで4カ月以上かかる場合があり、その間は凍結された口座からお金を引き出せないので注意が必要です。
老人ホームに入居するときに身元引受人がいない場合
多くの老人ホームでは入居するときに身元引受人が必要ですが、施設によっては身元引受人がいない場合、成年後見人を立てると入居できる場合があります。
ただし、成年後見人にはできないこともあります。
例えば、成年後見人を身元引受人や連帯保証人にはできません。
身元引受人は入居者が利用料を支払えなくなった場合、代わりに支払う連帯保証人を兼ねている場合もあります。
対して、成年後見人は契約や利用料の支払いなどはできますが、入居者が支払えなくなった料金の肩代わりはできません。
これは、成年後見人の役割が入居者の財産を管理し守ることであり、利用料を本人に代わって立て替え、その費用を本人に請求することは、双方の利益が反する状態となるため認められていないからです。
成年後見人を利用するときの注意点

成年後見人の利用には、途中でやめられない、利用にはお金がかかるなどのデメリットがあります。
成年後見人は途中でやめられない
成年後見制度は、一度利用を始めると、判断能力が低下した本人(被後見人)が回復し判断能力を取り戻すか、被後見人が亡くなるまで続き、途中でやめられないため注意しましょう。
例えば、銀行口座の解約のため成年後見人を立てた場合、銀行口座を解約する目的を果たしたからもう成年後見人はいらない、というわけにはいきません。
また、成年後見人となった人と意見が合わない、相性が合わないと感じても変更できません。
よく検討してから利用を始めましょう。
制度の利用にはお金がかかる
成年後見制度を利用する場合、契約時や申立時の手数料、成年後見人に支払う報酬など多くの費用がかかるため注意しましょう。
任意後見制度を利用するときには公正証書で契約をする必要があり、下記のような費用がかかります。[注1]
- 公正証書作成の基本手数料(1万1,000円)
- 登記嘱託手数料(1,400円)
- 登記所に納付する印紙代(2,600円)
- 本人に交付する正本などの証書代
- 郵送用の切手代
また、任意後見制度でも法定後見制度でも、家庭裁判所に申立をするときには下記のような手数料がかかります。[注1][注2]
- 申立手数料(800円)
- 登記手数料(任意後見制度は1,400円、法定後見制度は2,600円)
- 本人の状態を医学的に確認するための鑑定料(多くの場合10万円以下)
- 連絡用の郵便切手代
- 申立に必要な戸籍謄本、登記事項証明書などの書類発行費用
その他に、成年後見人となった人に毎月報酬を支払わなければならない場合があります。
親族が成年後見人となった場合は無報酬が多いですが、専門家が成年後見人となると毎月2万円~6万円を報酬として支払う必要があります。
報酬は被後見人の財産から支払うことが一般的ですが、被後見人の財産が少なく払えない場合は、家族が負担しなければなりません。
報酬の支払いは被後見人が亡くなるまで続くため、経済的負担が大きくなります。
継続して報酬を支払っていけるのか、利用前によく検討しましょう。
「あなたらしく」では老人ホーム以外のご相談も承っています。
お気軽にお問い合わせください。
>>[注1]厚生労働省 「任意後見制度とは(手続の流れ、費用)」
>>[注2]厚生労働省「法定後見制度とは(手続の流れ、費用)」










