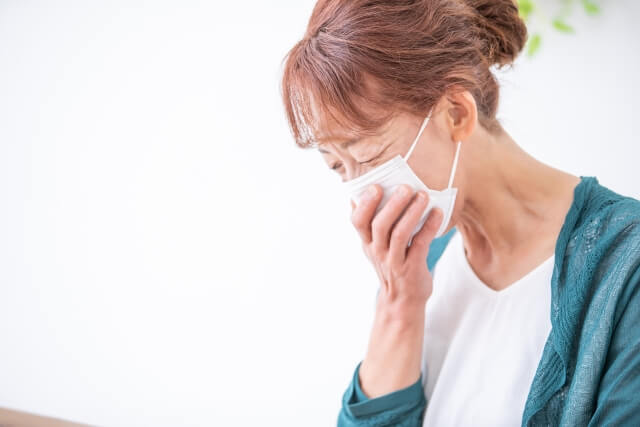老人ホームには多くの方が暮らしているため、ときに風邪などの感染症が蔓延してしまうこともあります。
高齢の方は軽い風邪がなかなか治らなかったり重篤化してしまったりすることがあるため、感染対策には十分に気を付けましょう。
この記事では、「老人ホームの風邪対策」について詳しくご紹介していきます。
老人ホームで発生しやすい感染症

老人ホームではときに、集団感染といった事態が起こる可能性があります。
まずは、老人ホームで発生しやすい、注意すべき感染症についてみていきましょう。
インフルエンザ
老人ホームで特に気を付けたい感染症の一つにインフルエンザがあります。
インフルエンザウイルスに感染することで発症するインフルエンザは、38度以上の高熱をはじめとした症状が急に現れるのが特徴的です。
インフルエンザの症状はさまざまで、具体的には倦怠感や頭痛、関節痛、咽頭痛、吐き気、咳、鼻水などが挙げられます。
また、合併症で肺炎や気管支炎、脳症などが起こるケースもあり、十分な注意が必要です。
感染性胃腸炎
感染性胃腸炎も、老人ホームで問題になりやすい感染症です。
日本国内でよくある感染性胃腸炎はノロウイルスやロタウイルスですが、アデノウイルスやエンテロウイルスなどの感染症が流行することもあります。
感染性胃腸炎の主な症状は、吐き気や嘔吐、下痢などです。
また、感染者の吐瀉物や便からウイルスが飛び散ることで、周囲の人も感染する恐れがあります。
ノロウイルスの感染性胃腸炎はワクチンによる予防ができず、感染力も強いです。
流行期となる冬場は、特に気を付けましょう。
肺炎
肺炎とは、肺の内部に炎症が起きることを指します。
肺炎を引き起こす細菌には、肺炎球菌やインフルエンザ菌、黄色ブドウ球菌、レジオネラ菌、結核菌などがあります。
これらの細菌が体内に入って感染症が起きると、肺にまで重篤な症状が及んでしまう恐れがあるのです。
免疫力の低い高齢者は、肺炎の症状がなかなか改善せず、長期にわたって療養が必要となることもあります。
重症化を避けるためにも、入居者が適切な治療を受けられるよう、老人ホーム側の体制を整えておくことが求められます。
結核
結核とは、結核菌の飛沫感染によって起こる症状です。
結核に感染すると熱や咳、痰などの症状が出ます。
ただし、結核の症状はすぐに現れるとは限りません。
結核菌が体の中に入り、数年が経過してから発症することもあるようです。
現在では結核の治療法が確立されており、感染した際の死亡率は高くないものの、合併症を起こした場合は深刻な症状が続くことがあります。
重篤化すると肺やリンパに症状が及ぶこともあるので、注意が必要です。
緑膿菌感染症
緑膿菌感染症は、健康な人の場合ならそれほど害がありません。
しかし、免疫力が弱まった高齢者が緑膿菌感染症にかかると、さまざまな症状が現れる恐れがあるため、注意しましょう。
緑膿菌感染症によって体に現れる影響の一つが、呼吸器系や血管への影響です。
症状が悪化した場合、肺組織に異常が起きることもあります。
また、緑膿菌感染症にかかると傷が治りにくくなり、傷周辺の組織が壊死するケースもあります。
症状が悪化すると敗血症などで亡くなる方もいるため、早めの治療が重要です。
尿路感染症
尿路感染症は、膀胱や尿道といった尿の通り道から感染が起きる病気です。
尿路感染症にかかると、残尿感や排尿痛、頻尿などの症状が現れます。
老人ホームで寝たきりの方やおむつの交換頻度が低い方は、細菌の増殖によって尿路感染症が悪化しやすくなります。
老人ホームにおける風邪予防対策

老人ホームでの感染を防ぐためには、以下のような「対策」が効果的です。
うがいや手洗い
うがいと手洗いは感染症対策の基本です。
外から帰ったときやトイレのあと、食事の前などに手を洗うだけでも、風邪のリスクを大幅に下げられます。
外出後は手洗いだけでなくうがいもして、口腔内に付着した菌を洗い流すことが大切です。
さらに、必要に応じてアルコールなどで手指を消毒すれば、より高い風邪予防効果が得られるでしょう。
検温
老人ホームでは検温を通して、入居者の体調を把握する必要があります。
検温を習慣化すれば、一人ひとりの発熱に気づきやすくなるためです。
また最近は、面会に訪れた人などを対象に、入口で体温を測定する機器を設置している老人ホームも増えてきました。
発熱している人の入館を防ぐことで、外部から細菌やウイルスが持ち込まれるリスクを下げられます。
消毒

不特定多数が触れる場所を、アルコールなどで消毒するのも効果的です。
室内のスイッチやボタン、手すりやドアノブなどに細菌やウイルスが付着すると、この部分に触れた人によって感染が拡大する恐れがあります。
そのため、老人ホームの介護スタッフや清掃スタッフは、多くの人が触れる部分を中心に定期的な消毒を行っています。
換気
室内の空気に漂う細菌やウイルスが、風邪の原因になることもあります。
風邪予防のためにも、こまめに換気して室内の空気を入れ替えることが大切です。
一般的に、1~2時間ごとに約10分ほど窓やドアを開けるようにすれば、室内の空気が入れ替わるといわれます。
とはいえ、窓を開けたままだと寒さを感じることもあるため、室温を調整しながら換気するのが望ましいでしょう。
排泄物や嘔吐物の処理
排泄物や嘔吐物を介して感染症が蔓延するケースもあります。
老人ホームで嘔吐した人がいたら、感染が広がらないよう、速やかな対処が求められます。
排泄物で洋服などが汚れたときには、すぐに新しいものに交換することも大切です。
また、老人ホームで感染症が流行しているときは、排泄物や嘔吐物からの感染が起きないよう十分注意しましょう。
予防接種
インフルエンザや肺炎球菌などの予防接種をしておくのも有効な対策法の一つです。
予防接種をしたからといって、感染症を完全に防げる訳ではありません。
しかし予防接種を受けておくことで、感染症にかかったときに症状が重症化するリスクを軽減できるとされています。
各感染症の流行期を見越して、定期的に予防接種を受けておくのがおすすめです。
入所中に風邪をひいたらどうする?

老人ホームの入所中に、風邪をひいてしまったときには、できるだけ安静にしてゆっくりと休みましょう。
高齢者は加齢によって体力や免疫力が低下しがちで、軽い風邪でも治癒が長引いてしまうことがあります。
また、深刻な合併症が起きてしまうケースもあるため、慎重に経過を見守りましょう。
特に、咳や痰の症状が悪化して呼吸器に異変が出るケースには注意が必要です。
呼吸器系の症状は重篤化しやすいため、早めの治療が大切です。
また、高齢者は体温調節機能の衰えによって、熱がそれほど上がらないことがあります。
「体温が低いから」と無理をした結果、急に症状が悪化する恐れもあるため、体調の良し悪しを熱だけで判断しないようにしましょう。
症状が気になるときは早めに介護スタッフに相談したり、医師の診察を受けたりすることも大切です。
医師が常駐している老人ホームを選べば、早い段階で適切な処置を受けられるでしょう。
手厚いケアを受けられる老人ホームをお探しなら、ぜひ「あなたらしく」をご利用ください。