内閣府の「高齢社会白書(平成29年)」によると、65歳以上の認知症患者の割合は年々増加しており、2025年には「約5人に1人」が認知症になるといわれています。
[注1]認知症にかかると健康な脳細胞が破壊され、記憶障害や見当識障害、感情表現の変化など、さまざまな症状が発生します。
認知症を予防するには、初期の徴候を見逃さないことが大切です。
本記事では、認知症の種類や主な症状、予防するためのポイントを分かりやすく解説します。
認知症の種類

認知症は「記憶障害など脳の認知機能障害により、日常生活に支障をきたすようになる疾患」のことです。
[注2]認知症といっても、以下のようにさまざまな種類があります。
- アルツハイマー型認知症
- レビー小体型認知症
- 前頭側頭型認知症
- 血管性認知症
- ビンスワンガー病
シニア世代の認知症でもっとも多いのが、「アルツハイマー型認知症」です。
認知症のうち、アルツハイマー型認知症が占める割合は67.6%で、約3人に2人の方が罹患しています。
[注3]ここでは、認知症の主な種類を解説していきます。
[注3]厚生労働省老健局「認知症施策の総合的な推進について(参考資料)」P3
アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型認知症は、脳内にアミロイドβと呼ばれるタンパク質が溜まり、健康な神経細胞が破壊される疾患です。
アルツハイマー型認知症が進むと脳が徐々に萎縮し、軽度のもの忘れから始まって、時間や場所の感覚がなくなるなどの見当識障害を発症します。
レビー小体型認知症

レビー小体型認知症は、脳内にレビ-小体と呼ばれるタンパク質が溜まり、神経細胞が破壊される疾患です。
アルツハイマー型認知症とよく似ていますが、レビー小体型認知症にかかると幻覚が見えたり、手足の震えや筋肉の拘縮などの症状が発生したりすることがあります。
また、レビー小体型認知症の患者の特徴として、歩幅が小刻みになる人が多く、転びやすくなるため日常生活に注意が必要です。
前頭側頭型認知症
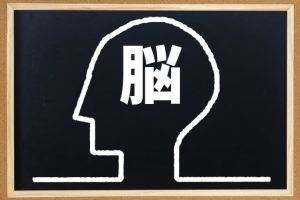
前頭側頭型認知症は、主に脳の前頭葉や側頭葉前方で神経細胞の減少が起こり、脳が萎縮してしまう疾患です。
脳の前頭葉は思考や判断能力、側頭葉は記憶や聴覚に関わる場所だといわれています。
前頭側頭型認知症が進行した場合、感情の抑制が効かなくなったり、万引きのような軽犯罪を起こしたりする可能性があります。
血管性認知症

脳血管性認知症(血管性認知症)は、脳梗塞や脳出血によって脳の血流が滞り、神経細胞が死滅することで発症します。
他の認知症と比べて、生活習慣との関わりが深く、予防するには規則正しい食事・運動・睡眠の習慣をつける必要があります。
ビンスワンガー病

発症率は高くないものの、深刻な症状をもたらすことがあるのがビンスワンガー病です。
ビンスワンガー病は、脳の広い範囲に白質病変(血流が不足し、酸素不足になった状態)が起きたもので、失禁、歩行障害、嚥下障害、手の震え、幻覚、妄想などのさまざまな症状が発生します。
血管性認知症と同様に、高血圧症などの生活習慣病と深い関わりがある疾患です。
認知症の症状

認知症には、脳細胞が破壊されることで直接発生する「中核症状」と、本人の性格や周囲環境などの影響で二次的に発生する「周辺症状」の2種類の症状があります。
厚生労働省によると、認知症の中核症状はさらに以下の「5つ」に分類されます。[注4]
- 記憶障害
- 見当識障害
- 理解・判断力の障害
- 実行機能障害
- 感情表現の変化
ここでは、認知症の「主な5つの症状」を簡単に解説します。
記憶障害

認知症が進むと、健康な神経細胞が破壊されることで、記憶障害が発生します。
加齢によるもの忘れと違って、認知症の記憶障害は新しいことを覚えられず、症状が進行すると過去に覚えていたことも忘れていきます。
見当識障害

記憶障害と並んで、認知症になると見当識障害が現れるケースがほとんどです。
見当識障害とは、時間(いつ)や場所(どこ)を正常に認識できなくなったり、周囲の人との関係を思い出せなくなったりする症状です。
見当識障害を発症すると、異常行動や徘徊が見られるため、自立した暮らしを送ることが困難になります。
理解・判断力の障害

認知症の患者は、正常な理解力や判断能力が失われます。
例えば、考える速度が著しく低下したり、2つ以上の物事を同時に処理できなくなったりします。
また、予想外の出来事に直面すると、パニックを起こすことがあるのも認知症患者の特徴です。
家族のパニックをきっかけとして、認知症に罹っていることが発覚するケースもあります。
実行機能障害

実行機能障害とは、なにかをする前に計画を立てたり、順序立てて行動したりすることができない状態です。
直前のことを忘れてしまうため、行動に脈略がなくなり、日常生活を送るのが難しくなります。
例えば、「炊飯器でご飯を炊く間におかずを作る」「スーパーで具材を買ってからみそ汁を作る」といった計画的な行動ができなくなります。
感情表現の変化

認知症の患者には、感情表現の変化も見られます。
特に感情の変化が少なくなり、喜怒哀楽の感情をあまり示さなくなる人がほとんどです。
一方、いきなり怒り出すなど、予測不可能な感情を示す人もいます。
認知症の症状の中でも、比較的見た目に現れやすい症状の一つです。
認知症を予防するためのポイント

認知症を予防するには、初期症状に気づくことが大切です。
特にアルツハイマー型認知症の場合、以下の4つの初期症状があることが知られています。[注5]
| 早期徴候 | 具体例 |
|---|---|
| 物忘れ(記憶障害) | ・置き忘れ、しまい忘れ ・大切な約束事を忘れる ・言ったことを忘れて何回も言う ・何回も聞いてくる |
| 怒りっぽい(易怒性) | ・些細なことですぐに怒る ・以前は大人しい性格だったが、この頃怒りっぽい ・ちょっと注意すると、ものすごい剣幕で怒る |
| 日時の概念が混乱している | ・何回も日時や曜日を聞いてくるようになった ・慣れ親しんでいるはずのお稽古事の曜日を確認するようになった |
| 自発性の低下、意欲の減退 | ・長年慣れ親しんだ趣味やお稽古事に関心がなくなった ・一日中テレビを眺めている ・新聞やテレビを見なくなった ・家でうとうとしていることが多い ・外出しなくなった ・親しい友人との付き合いをしなくなった |
初期の認知症は軽度認知障害(MCI)と呼ばれ、物忘れなどの症状はありますが、日常生活を送る上で支障はありません。
また、軽度認知障害の方が治療を受け、正常なレベルに回復した症例もあります。
認知症の初期症状を知り、なるべく早期に治療を受けることが大切です。
【まとめ】認知症の種類や初期症状を知り、予防に向けた取り組みを
認知症の患者は年々増えています。
認知症は加齢によるもの忘れと違って、健康な脳細胞が死んだり働きが悪くなったりして、正常な脳機能が失われる「脳の病気」です。
認知症の初期症状を知り、早めに治療を行うことが大切になります。
認知症が進行すると、記憶障害や見当識障害、感情表現の変化などの中核症状が生じ、自立した暮らしを送ることが困難になります。
家族に認知症の方がいる場合は、認知症ケアが可能な老人ホームを探しましょう。
老人ホームを探す場合は、「あなたらしく」がおすすめです。










