あなたらしく
介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受けなければなりません。
認定基準や仕組みについて知っておけば、いざというとき困ることもないでしょう。
この記事では、「要介護認定基準」や「仕組み」について詳しく解説します。
要介護認定を受けるときの流れについても解説しますので、ぜひチェックしておきましょう。
要介護認定とは?

要介護認定とは、日常生活を送る上で、どの程度のサポートが必要なのかを客観的に判断する仕組みのことです。
要介護認定においては、身体機能・生活機能・認知機能などをチェックし、「要支援1〜2」、「要介護1〜5」などと数値化します。
要支援や要介護の認定を受けると、1〜3割の自己負担でさまざまな介護保険サービスを利用可能です。
要支援・要介護ともに、数値が大きくなるほど介護度は高くなり、支給限度基準額も高額になります。
要支援や要介護の具体的な違いは以下のとおりです。
要支援1

要支援とは、ある程度は自立した生活ができるものの、部分的な介護が必要な状態です。
要支援と認定された場合は、要介護状態になるのを防ぐための介護予防サービスを利用できます。
「要支援1」は、要介護認定のなかで最も軽度な状態です。
具体的には、食事や排泄などは基本的に自分で行うことができ、見守りや簡単な手助けのみが必要な状態を指します。
身体的な衰えがあり、立ち上がるときのサポートが必要なケースも多いでしょう。
要支援2
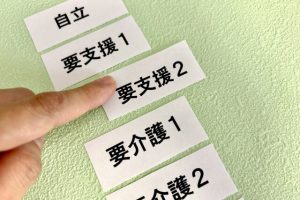
「要支援2」は、複雑な動作をする際のサポートが必要な状態です。
要支援1と同様、食事や排泄などは自立して行えますが、身体機能はより低下しています。
歩くときに杖が必要であったり、片足で立つとふらついてしまったりするケースも多いでしょう。
着替えや入浴の際に、手助けを必要とすることもあります。
要介護1

「要介護」は5段階に分けられています。
要支援と要介護の大きな違いは、身体機能だけではなく、認知機能も低下していることです。
理解力や思考力が低くなっていたり、認知症の疑いがあったりすると要介護と認定されます。
「要介護1」は、生活の一部でサポートが必要な状態です。
歩くときや入浴時にサポートが必要な場合もあります。
認知機能が低下しており、会話はできますが、話が噛み合わない場面もあるでしょう。
要介護2
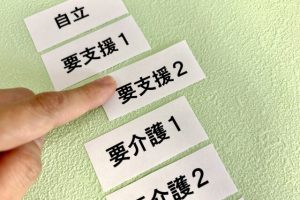
「要介護2」は、身体機能や思考力がより低下した状態です。
食事や排泄などについてもサポートが必要になり、自宅で介護していると負担を感じるかもしれません。
テレビの内容を理解できない、爪を切るような細かい動作ができないなど、自立した生活が難しくなっていきます。
要介護3

「要介護3」は、食事や排泄などの基本動作だけではなく、生活全般のサポートが必要な状態です。
スムーズに歩いたり、自分で着替えたりするのは難しいでしょう。
見守るだけではなく、歩く際に身体を支えるなどのサポートが必要です。
記憶力や理解力の低下も見られます。
認知症が進行し、深夜に徘徊したり奇声を出したりする高齢者もいるでしょう。
要介護4

「要介護4」は、ほとんどの動作に対して介助が必要な状態です。
ほぼ寝たきりとなり、自分で起き上がったり立ち上がったりすることができない人も多いでしょう。
座った状態を保てない場合もあり、自宅での介護には大きな負担を感じるかもしれません。
認知機能も低下しており、うまくコミュニケーションが取れないケースも多いでしょう。
徘徊・奇声・妄想といった問題行動も増えるため、在宅介護に限界を感じることもあります。
要介護5

「要介護5」は、要介護認定のなかで最も重い状態です。
さまざまな介助を受けなければ、日常的な生活を送ることはできません。
排泄のためにおむつを使用したり、食べ物を飲み込むのが難しくなったりする場合もあります。
重度の認知症であるケースが多く、意志の疎通も簡単にはできません。
徘徊することも多いため、思わぬ場所で怪我をしないよう注意が必要です。
要介護の認定基準

要介護認定の際は、それぞれの介助にかかる時間を基準として認定を行います。
認定時にチェックされる介助項目は、次の「5つ」です。
| 直接生活介助 | 食事・入浴・排泄・着替えなど |
| 間接生活介助 | 洗濯・掃除・会話など |
| 問題行動関連介助 | 徘徊・暴力・不潔行為への対応など |
| 機能訓練関連行為 | 歩行訓練・寝返り訓練など |
| 医療関連行為 | 服薬管理・輸液管理など |
これらの介助にかかる時間を算出し、要支援や要介護を認定します。
専門用語では「要介護認定等基準時間」と呼ばれます。
要介護度と要介護認定等基準時間の関係は以下のとおりです。[注1]
| 要介護度 | 要介護認定等基準時間 |
|---|---|
| 要支援 | 25分以上32分未満 |
| 要介護1 | 32分以上50分未満 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 |
| 要介護5 | 110分以上 |
要介護認定を受ける流れ

要介護認定を受けるときは、各市区町村の窓口で申請しなければなりません。
その後、訪問調査や一次判定・二次判定を受けます。
具体的な流れは、次のとおりです。
各市区町村の窓口で申請する

要介護認定の申請は、各市区町村の窓口で行います。
場所がわからない場合は、総合窓口で聞いてみましょう。
申請の際は、申請書や介護保険の被保険者証などが必要です。
申請料は必要ありません。
本人による申請が難しい場合は、代理人を立てることも可能です。
訪問調査を受ける

訪問調査では、身体機能や認知機能、日常生活の状況などについてヒアリングされます。
ケアマネージャーなどの専門職が自宅まで来てくれるのが一般的です。
訪問調査を受けるときは、普段の生活スタイルや介護の状況を正確に伝えなければなりません。
自分でできること・できないことや重要なポイントを、事前にまとめておくとよいでしょう。
主治医の意見書を作成する

訪問調査が終了したら、市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。
基本的にはかかりつけ医が作成しますが、いない場合は別途診察を受ける必要があります。
定期的に検診を受けて、信頼できる主治医を見つけておくと安心です。
一次判定を受ける

要介護認定における一次判定は、コンピュータによって行われます。
訪問調査におけるヒアリング項目や、主治医の意見書の内容を入力することで判定されます。
二次判定を受ける

二次判定は、福祉や医療の専門家によって行われます。
一次判定の結果はもちろん、訪問調査の内容も慎重に審査されるため、正確な情報を伝えるようにしましょう。
【まとめ】要介護の認定基準の仕組みを知って適切な対応をしよう!
今回は、要介護認定の仕組みや基準について解説しました。
要支援や要介護と認定されると、さまざまな介護サービスを受けられます
自宅ですべての介助を行うと負担が大きくなるため、要介護認定をうまく利用して介助に関する負担を減らしましょう。
介護の負担を軽減するためには、老人ホームへの入所を検討することも重要です。
さまざまな老人ホームがあり、受けられるサービスは異なるため、状況に合った施設を選びましょう。
老人ホーム探しを始めるのなら、「あなたらしく」のご利用がおすすめです。










