「要介護認定の更新をしたら、要介護1から2になった」
「要介護1と2の違いってなんだろう?」
このように、要介護1と2の違いがわからず、悩んでいる方も多いでしょう。
要介護2は、要介護1と比べて立ち上がりや歩行が不安定で、入浴・排泄のほか日常生活の一部もしくは全部に介助を必要とする状態を指します。
要介護2の場合、要介護1では借りられない、車椅子や介護用ベッドのレンタルが可能です。
本記事では、要介護1と2の違いをまとめた一覧表をもとにわかりやすく解説します。
要介護2に認定された家族の施設入所をお考えの方は、老人ホーム選びの無料サポートを受けられる「あなたらしく」の活用がおすすめです。
介護制度や施設の選び方など、介護にまつわる相談だけでも対応してもらえます。
要介護1と2の違い|一覧表で紹介
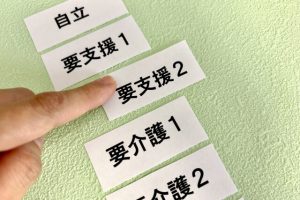
要介護1と2の違いは、以下の通りです。
| 要介護2 | 条件 | |
|---|---|---|
| 身体の状態 |
・食事や排泄など身の回りのことは自分で行える ・入浴で一部介助が必要 ・起立や歩行で介助が必要 ・認知機能の低下がみられる |
・食事や排泄、入浴において一部介助が必要 ・着替えや爪切り、起立、歩行において介助が必要 ・認知機能の低下、問題行動がみられる |
| 利用できる介護保険サービス |
[介護の相談・ケアプラン作成] ・居宅介護支援 [自宅に訪問] ・訪問介護 ・訪問入浴 ・訪問看護 ・訪問リハビリ ・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 [施設に通う] ・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリ ・地域密着型通所介護 ・療養通所介護 ・認知症対応型通所介護 [訪問・通所・宿泊を組み合わせたもの] ・小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) [短期間の宿泊] ・短期入所生活介護(ショートステイ) ・短期入所療養介護 [施設で生活] ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設(老健) ・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等) ・介護医療院 ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) [地域密着型サービス:地域に密着した小規模な施設] ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 [福祉用具の貸与・販売] ・福祉用具貸与 ・特定福祉用具販売 |
|
| 入居できる施設 |
[公的な施設] ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・グループホーム ・軽費老人ホーム [民間施設] ・介護付き有料老人ホーム ・住宅型有料老人ホーム ・サービス付き高齢者住宅 |
|
| 支給限度額 | 167,650円 | 197,050円 |
※参照:公表されている介護サービスについて|介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
要介護1と2の違いについて、以下「4つ」の項目別にくわしく解説します。
- 1. 身体の状態
- 2. 利用できる介護保険サービス
- 3. 入居できる施設
- 4. 支給限度額
①身体の状態
要介護1と2の違いとして、身の回りのことを自分で行える身体の状態であるかが挙げられます。
要介護1と認定された方は、入浴や起立、歩行時に一部介助が必要なものの、食事や排泄などの身の回りのことは自分で行えます。
一方で、要介護2の方は食事や着替え、爪切りなど身の回りの動作に見守りや介助を必要とする状態です。
認知機能の低下から問題行動が見られる場合もあり、服薬や金銭管理などの複雑な動作を1人で行うのは難しくなります。
なお、要介護2の状態については、以下の記事でもくわしく解説しています。
②利用できる介護保険サービス
要介護1と2の違いは、利用できる介護保険サービスのうち、レンタルできる福祉用具の種類が異なる点です。
要介護1と認定された方がレンタルできる福祉用具は、手すりやスロープ・歩行補助杖などに限られます。
要介護2の方であれば、要介護1認定がレンタルできる福祉用具に加え、車椅子や介護用ベッドのレンタルが可能です。
なお、そのほか利用できる介護保険サービスは要介護1、2ともに同様となります。
③入居できる施設
要介護1と2で入居できる施設に違いはなく、介護医療院やグループホーム、介護付き有料老人ホームなどが挙げられます。
要介護1、2ともに、要介護3以上の認定を受けていることを条件とする、特別養護老人ホームには入居できません。
- 【要介護1と2で入居できる施設】
- [公的な施設]
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- グループホーム
- 軽費老人ホーム
- [民間施設]
- 介護付き有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者住宅
要介護2の家族に合う老人ホームを探している方は、老人ホーム選びのプロ・あなたらしくも活用しましょう。
介護に精通したスタッフが1人ひとりのニーズに最適な施設を選定し、入居後まで一貫してサポートします。
高齢者住宅の種類や特徴については、以下の記事も参考にしてください。
④支給限度額
要介護1と2の違いとして、支給限度額が異なる点が挙げられます。
要介護1と2の支給限度額は、以下の通りです。
- 要介護1:167,650円
- 要介護2:197,050円
支給限度額とは、介護保険内で利用できる介護サービスの上限金額を指します。
限度額の範囲内であれば、1〜3割の自己負担で介護サービスを利用可能です。
1単位10円、自己負担1割の場合、ひと月の自己負担額は以下を参考にしてください。
- 要介護1:16,765円
- 要介護2:19,705円
※参照:サービスにかかる利用料|介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
支給限度額を超えて介護サービスを利用した分の利用料は、全額自己負担となるため注意が必要です。
要介護1と2のケアプラン例と費用の目安

要介護1と2のケアプラン例と費用の目安を紹介します。
これらの内容を参考に、担当のケアマネージャーに相談しながら、自分や家族に最適な介護サービスの利用を検討してください。
要介護1のケアプラン例
要介護1のケアプランとして、在宅で訪問介護やデイサービスを利用する例を紹介します。
| サービス | 回数 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 訪問介護 | 週に4回(月に20回) | 6,840円 |
| 通所介護(デイサービス) | 週に3回(月に12回) | 8,676円 |
| 福祉用具貸与(手すりやスロープなど) | ひと月あたり | 806円 |
| 自己負担額計 | 16,322円 | |
※1単位10円、自己負担1割とした場合
※参照:概算料金の試算||介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
上記の例であれば、要介護1の支給限度額内における介護サービスの利用が可能です。
なお、デイサービスでの食事代やサービス加算が別途でかかります。
要介護2のケアプラン例
要介護2のケアプラン例は、以下の通りです。
| サービス | 回数 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 訪問介護 | 週に4回(月に20回) | 6,740円 |
| 通所介護(デイサービス) | 週に4回(月に20回) | 10,044円 |
| 福祉用具貸与(手すりやスロープなど) | ひと月あたり | 1,377円 |
| 自己負担額計 | 18,161円 | |
※1単位10円、自己負担1割とした場合
※参照:概算料金の試算||介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
介護サービスを利用する流れ

介護サービスを利用する流れは、以下を参考にしましょう。
- 1. 要介護認定を受ける
- 2. 居宅介護支援事業所でケアプランを作成してもらう
- 3. 希望する施設と契約する
- 4. 介護サービス利用開始
要介護度や家庭環境に応じて適切な介護サービスを受けるために、ケアマネージャーによるケアプランの作成が必須となります。
利用を希望する介護施設や事業者と契約後、サービスの利用が開始される流れです。
要介護1と2の違いを把握して適切な介護サービスを受けよう

要介護1と2の違いは、身の回りのことを自分で行える身体の状態であるかどうかです。
要介護1認定の方は、日常生活の一部動作に見守りや介助が必要なものの、食事や排泄など身の回りのことは自分で行えます。
一方で要介護2と認定された方は、食事や着替えのほか、服薬、金銭管理など複雑な身の回りの動作に介助が必要です。
要介護1と2では、レンタルできる福祉用具やひと月の支給限度額も異なります。
本記事で紹介したケアプラン例も参考に、自分や家族に適切な介護サービスを受けられるよう、ケアマネージャーに相談しましょう。
なお、老人ホーム選びに苦戦している方には、あなたらしくの無料サポートの活用がおすすめです。
専門スタッフが地域に根付いた情報をもとに、公平中立かつ客観的にあなたにぴったりの老人ホームを選定します。










