要介護と認定されると、介護保険制度を利用してさまざまなサービスを受けられるようになりますが、利用可能なサービスや給付限度額は要介護度によって異なります。
では、要介護2と認定された場合、どのようなサービスを受けられるのでしょうか。
本記事では、「要介護2における心身の状態や認定の基準、利用できるサービス」について分かりやすく解説します。
要介護2における心身の状態

要介護2とは、日常的な動作は自力で行えるものの、要所で介助を必要とする状態を指します。
例えば、身体機能の低下などにより、炊事や洗濯、掃除といった基本的な家事をこなすのが困難になる、自力で立つ・歩くといった行動が難しくなる、爪切りや着替えなどに介助が必要になるケースなどです。
また、体の機能だけでなく、認知症の初期症状が見られる場合もあります。
例えば、以前は問題なくできていた料理の手順を思い出せない、テレビや新聞の内容を理解するのが難しい、レジで計算できず、細かいお金での支払いができなくなったなど。
このような症状が一時的ではなく、日頃から頻繁に見られるのが要介護2の主な特徴です。
要介護1との違い
要介護2の前段階である要介護1は、日常生活上の基本的な動作についてはほぼ自分で行えるものの、要支援状態よりも日常生活動作を行う能力が低下しており、部分的な介護が必要となる状態のことです。
認知症の初期症状は見られないことと、見守りや介助が必要なシーンが要介護2より限定的であるところに違いがあります。
体の状態によっては、排泄や入浴などで見守りや介助が必要になるため、シーンに応じて介助サービスを利用することになります。
要介護2の認定基準
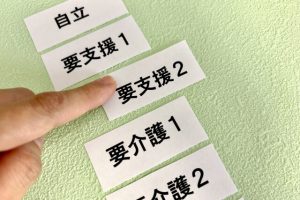
要介護認定とは、介護サービスの必要度がどのくらいかを客観的かつ公平に判断するためのものです。
介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定の申請を行い、要介護者であると認定してもらう必要があります。
要介護認定はコンピューターによる一次判定と、それを基に保健医療福祉の学識経験者が実施する二次判定の二段階判定を採用しています。
一次判定の基準
一次判定は、申請者の認定調査の結果を基に、介護老人福祉施設や介護療養型医療施設などに入所している3,500人の高齢者に対して行った「1分間のタイムスタディ・データ」から介護サービスの必要度を推計します。
認定調査の具体的な例を挙げると、「食事摂取」についての調査項目があり、自立して食事摂取できるなら左、一部または全ての介助が必要なら右と、状況に応じて枝分かれしていきます。
このような樹形モデルの認定調査を行った結果、割り出された要介護認定等基準時間を基に、要支援度・要介護度を判定する仕組みです。
要介護認定等基準時間とは、心身の状態から推計される介護の手間を「分」で示した指標です。
時間が長いほど介護の手間がかかると判断され、要介護度も高くなります。
要介護2の基準は「50分以上70分未満」です。
ただし、この時間は実際の介護時間や、利用できるサービスの時間と必ずしも一致するわけではないため注意が必要です。
二次判定
二次判定は、保健医療福祉の学識経験者5人程度で構成された介護認定審査会で行われます。
審査会では、一次判定の結果に加え、申請者の主治医が作成した意見書や、訪問調査の際に調査員が記載した特記事項などの情報を基に審査が行われています。
具体的には、学識経験者が各々の専門性を駆使して、その人が要支援・要介護者であるかどうか、どの程度の介護が必要な状態なのかを審査する仕組みです。
介護認定は、この二次判定の結果が基に行われ、要支援・要介護と認定された場合は市区町村を通じて本人のその旨が通知されます。
介護認定基準については、以下の記事でも説明しているのでぜひご覧ください。
要介護認定はどのように行われるの?認定基準や仕組みを解説
要介護2で受けられるサービス

要介護2に認定されると、介護老人保健施設や、介護療養型医療施設、有料老人ホームなどの介護福祉施設に入所することが可能になります。
また、日常的な身の回りの世話や介助、介護などのサービスを受けれる他、医療サービスなども利用することが可能です。
ここでは、「要介護2と認定された方が受けられる具体的なサービス」を紹介します。
在宅サービス
「在宅サービス」は、各々の専門家が利用者の自宅を訪問し、必要なサービスを提供します。
具体的なサービス内容は以下の通りです。
- 訪問介護
- 夜間対応型訪問介護
- 訪問看護
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
これらのサービスを利用すれば、利用者は自宅にいながら食事や入浴、排泄の介助を受けたり、炊事・洗濯・掃除を代行してもらったり、心身機能の維持や回復に努めたりすることができます。
通所サービス
「通所サービス」とは、利用者が介護福祉施設に通ってさまざまなサービスを受けることです。
具体的なサービス内容は以下の通りです。
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 療養通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 地域密着型通所介護
通所サービスは、施設ごとに受けられるサービスに違いがあり、例えばデイサービスでは食事・入浴などの介助や機能訓練などを受けられます。
一方、デイケアは心身機能を維持・回復させるためのリハビリテーションを主な目的としており、併せて食事や入浴などの支援も受けることが可能です。
このように、施設によって趣旨に違いがあるため、利用者のニーズに合わせてサービスを選択しましょう。
例えば、何らかの疾患を持つ方は療養通所介護、認知症を患っている方は認知症対応型通所介護の利用が適しています。
訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス
要介護2に認定されると、小規模多機能型居宅介護や、看護小規模多機能型居宅介護といった訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービスを利用可能になります。
小規模多機能型居宅介護は施設への通所をメインに、様態や希望に応じて訪問介護を受けたり、施設に短期間宿泊したりできます。
家庭的な環境や地域の方との交流の下、日常生活に必要な支援を受けたり、機能訓練を実施したりできるところが特徴です。
一方の看護小規模多機能型居宅介護とは、前述した小規模多機能型居宅介護に訪問看護サービスを組み合わせたものです。
介護だけでなく、自宅にて看護サービスも受けられるため、健康管理や医療処置が必要な方に適しています。
その他サービス
介護保険を適用して、車椅子や特殊寝台をレンタルしたり、自宅に手すりやスロープを設置したりすることが可能になります。
また、入浴補助用具や歩行器といった特定福祉用具の購入も介護保険の適用対象です。
以上、要介護2で受けられるサービスについて説明しましたが、実際に利用できるサービスの内容や費用は施設ごとに異なります。
数ある施設の中から、利用者のニーズや予算に合った施設を探すのには手間がかかりがちです。
「なかなか時間が取れない」「何を基準にして選べばいいか分からない」という方は施設探しのプロに相談しましょう。
老人ホーム検索サイト「あなたらしく」では、老人ホーム探しのプロがニーズ・目的のヒアリングから施設探し、見学の同行、入所後のアフターフォローに至るまで、しっかりサポートいたします。
サポートサービスは無料で利用することができます。
「要介護2と認定された家族に合った施設を探したい」といったご要望がある方は、ぜひ「あなたらしく」のサービスをご利用ください。










