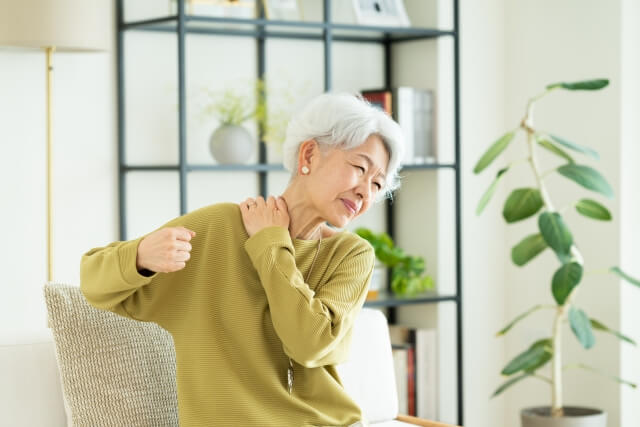要介護3は日常の動作が1人でできなくなり、行動のほぼ全てに介助が必要となる状態です。
認知症の症状もはっきりと現れていることが多いため、要介護3は介護が本格的となる一つの節目とされています。
介護をする方の精神的・肉体的な負担も増すため、要介護3となった方の状態、介護をする方の状況などを踏まえて適切な介護サービスを選択し、長期にわたる介護に備えましょう。
今回は「要介護3の状態」、認定基準や利用できるサービスについて解説します。
要介護3における高齢者の状態

要介護3の高齢者には、身体面、精神面で次のような症状が見られることがあります。
| 身体面の状態 |
・食事・入浴・排泄・着替え・歯磨きなどが1人ではできない ・足腰が不安定になり自力で立ち上がるのが難しい ・自力で歩くのが難しい ・立ち姿勢を保ったままではいられない ・歩行器や車いすを使用している |
| 精神面の状態 |
・判断力や記憶力が低下する ・時間や場所、人が認識できなくなってくる ・意思疎通が困難になる ・幻覚・妄想がある ・大声・奇声を上げる ・暴力・暴言がある ・イライラがある ・徘徊をする ・失禁がある ・誤食をする ・不潔行為がある |
要介護1~5の中間に位置する要介護3は、要介護の一つの節目とされています。
要介護2までは部分的なサポートだけでできていたことが、要介護3では全面的な介助なしでは1人でできなくなり、基本的に24時間介護が必要な状態となるためです。
さらに、認知機能の低下によって認知症の症状が現れ、問題行動を取る可能性が高くなってきます。
そのため、「要介護3」は本格的な介護開始の目安とされています。
介護する家族に精神的・肉体的な負担が今まで以上に掛かるため、さまざまな介護サービスの利用を本格的に検討する時期とも言えるでしょう。
要介護3と認定される基準

要介護3と認定される基準は、厚生労働省が定めた要介護認定等基準時間が、70分以上90分未満、またはこれに相当すると認められる状態です。[注1]
要介護認定等基準時間とは、介護に掛かる手間や労力を時間で表したもので、実際に家や施設で介護に掛かる時間とは異なります。
要介護認定等基準時間は、下記の、生活に関わる5つの行為から計算されます。
| 直接生活介助 | 入浴や排泄、食事などの介護 |
| 間接生活介助 | 洗濯、掃除などの家事援助 |
| BPSD関連行為 (問題行動関連行為) |
徘徊した場合の探索、不潔な行為をした後の始末など |
| 機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練などの機能訓練 |
| 医療関連行為 | 輸液の管理、褥瘡(じょくそう=床ずれ)の処置など診療の補助 |
5つの各行為にかかる時間を合計して、要介護認定等基準時間を割り出し、要介護度を判定します。
もし認知症の症状が見られる場合は、この要介護認定等基準時間の合計に対し、認知症の程度に応じた介護時間が加算されるという仕組みです。
要介護認定等基準時間と要介護認定までの流れについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。
『要介護認定はどのように行われるの?認定基準や仕組みを解説』
⇒ ご参照ください。
要介護3で受けられるサービス

要介護3で受けられるサービスには、訪問・通所・ショートステイ・福祉用具のレンタルや購入・施設への入居などがあります。
訪問サービス
訪問サービスは自宅で受けられる介護サービスで、自宅でサービスを受けたい場合や、施設に通うことが難しい場合に利用すると良いでしょう。
| 訪問介護 | 自宅で生活しながら、訪問介護員による身体介護、生活サポートを受けられる |
| 訪問入浴介護 | 看護や介護のスタッフが専用の浴槽を利用者の自宅に持参し、入浴介護を行う |
| 訪問看護 | 看護師や保健師が利用者の自宅を訪問し、血圧や脈拍の測定、病状チェック、リハビリテーションなどを行う |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などによる、リハビリテーションを自宅で受けられる |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間に訪問介護員が自宅に訪問し、排泄介助や安否確認を行う、夜間の緊急時に訪問介護員に来てもらえる、などのサービスがある |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護サービスや世話、診療補助を、24時間365日必要なタイミングで、介護スタッフと看護師が連携して行う |
通所サービス
通所サービスは施設に通って受けられるサービスで、自宅にいることが多い高齢者の孤独感の解消や、心身機能の維持・回復、介護する家族の負担軽減を目的として提供されます。
| 通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンターに通い、食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなどのサービスを日帰りで受けられる |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 老人保健施設や病院などの施設に通い、機能訓練、食事、入浴などのサービスを日帰りで受けられる |
| 地域密着型通所介護 | 住まいのある市町村の密着型通所介護施設に通い、機能訓練、食事、入浴などのサービスを日帰りで受けられる |
| 療養通所介護 | 難病・認知症・末期がん患者などが療養通所介護の施設に通い、機能訓練や口腔機能向上サービス、食事、入浴などのサービスを日帰りで受けられる |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方がデイサービスやグループホームに通い、食事や入浴、機能訓練など専門的なケアを日帰りで受けられる |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模施設への通いを中心に、短期間の宿泊や、訪問介護も組み合わせて日常生活のサポートや機能訓練を行う |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 施設への通いを中心に、短期間の宿泊や訪問介護、訪問看護を組み合わせた、介護と看護一体型のサービスを受けられる |
ショートステイ
ショートステイは短期間、施設に宿泊できるサービスです。
介護する家族の負担が大きい時や、冠婚葬祭などで家を空ける場合などに利用すると良いでしょう。
| 短期入所生活介護 | 連続利用日数30日を上限として、常に介護が必要な方を施設に受け入れ、日常生活のサポートや機能訓練を提供する |
| 短期入所療養介護 | 医療機関や介護老人保健施設などが、連続利用日数30日を上限として利用者を受け入れ、日常の世話や医療、看護、機能訓練などを提供する |
福祉用具のレンタル費・購入費の支給
要介護3では、福祉用具のレンタル費や購入費の支給が受けられます。
レンタルできる福祉用具には車いすや介護用ベッド、歩行器など計13種類があり、レンタル料金の1割~3割を利用者が負担するだけでレンタル可能です。
シャワーチェアやポータブルトイレなど、直接肌に触れる福祉用具はレンタルできないため、購入します。
購入費の全額を利用者が一旦支払った後、購入費の7割~9割が介護保険から払い戻しされます。
「年間10万円が上限」です。
日常生活のほぼ全てに介助が必要となる要介護3では、福祉用具があれば家族の介護負担の軽減に役立つため、福祉用具のレンタルや購入を検討してみると良いでしょう。
施設への入居
施設に入居し、生活上のサポートや機能訓練などを受けられるサービスです。
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 常に介護が必要な方が入居し、生活上のサポート、機能訓練、療養上の世話などのサービスを受けられる |
| 介護老人保健施設 | 3カ月の期間を目安として入居し、利用者はリハビリテーションや医療、介護などのサービスを受けられる |
| 特定施設入居者生活介護 | 指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームに入居し、生活上のサポートや機能訓練などのサービスを受けられる |
| 介護医療院 | 長期間療養が必要な人を受け入れ、看護、介護、機能訓練、必要な医療を提供する施設 |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 1つの生活空間で、5~9人の利用者が共同生活を送る施設。少人数のアットホームな雰囲気の中で、認知症の専門的なサポートを受けながら生活できる |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員30人未満の特別養護老人ホームに入居し、日常生活のサポートや機能訓練などを受けながら生活できる |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 指定を受けた定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームに入居し、生活サポートや機能訓練などを受けながら生活できる |
要介護3は介護する方の負担が大きくなるため、施設への入居を検討する方も多くなっています。
施設には、大人数の施設から小規模な施設までさまざまな種類があり、中でも特別養護老人ホームは、要介護3から入居できる施設です。
施設の入居を希望する場合はあらかじめ見学を行い、施設の雰囲気やサービス内容が利用者にあった施設を選ぶと良いでしょう。
要介護3に認定され、入居する施設をお探しの方は、「あなたらしく」をご活用ください。